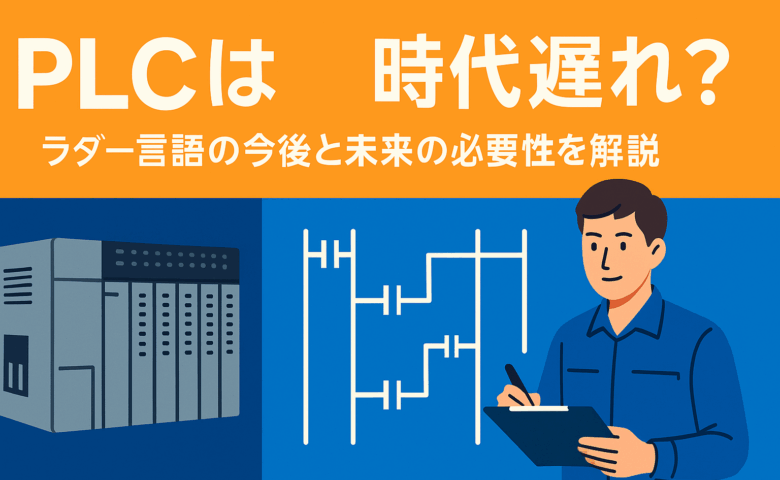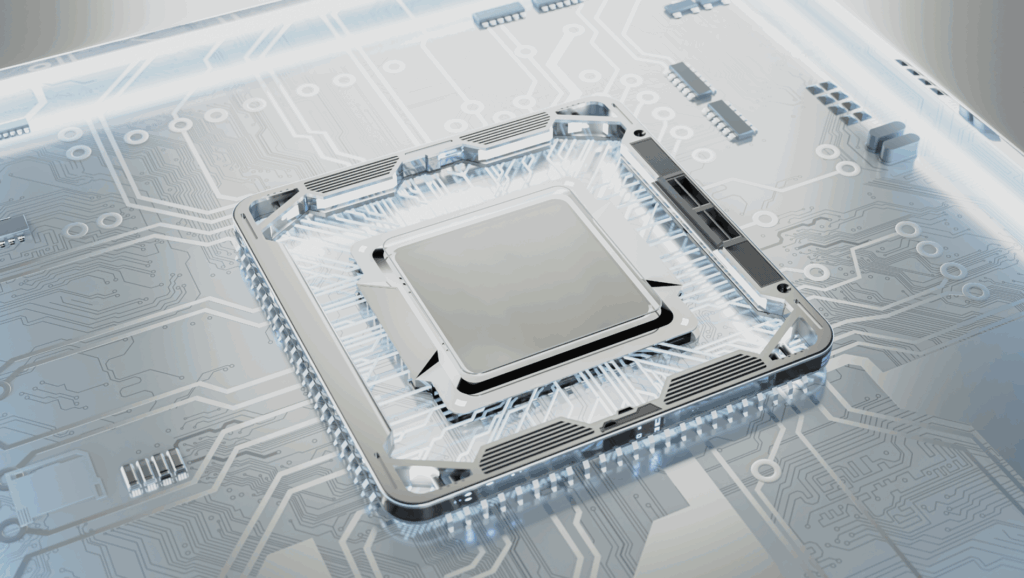
- INDEX目次
目次【非表示】
- 1.チップレットが注目される理由|半導体微細化の限界を打破
- 2.チップレット技術がもたらす4つのメリット
- 2-1.メリット1:異なる機能のチップを自由に組み合わせられる
- 2-2.メリット2:不良品率を下げて生産効率(歩留まり)を改善
- 2-3.メリット3:開発期間の短縮と製造コストの削減を実現
- 2-4.メリット4:柔軟な設計で多様なニーズに対応可能に
- 3.チップレット導入における3つの課題(デメリット)
- 3-1.課題1:チップ間の高速なデータ通信技術が不可欠
- 3-2.課題2:複数のチップを統合する設計・検証が複雑化
- 3-3.課題3:高度な実装(パッケージング)技術が求められる
- 4.チップレットの最新動向と今後の展望
- 4-1.世界的な開発競争と標準化に向けた取り組み
- 4-2.さらなる性能向上を支えるパッケージング技術の進化
- 4-3.AIやデータセンターなど多様な分野への応用拡大
- 4-4.まとめ
チップレットとは、複数の小さな半導体チップ(ダイ)を組み合わせて、一つの大きなチップのように機能させる技術です。
モノリシック構造とは異なり、機能ごとに分割した小型チップを基板上に集積し、一つのパッケージとして動作させます。
この技術は、微細化の限界によるコスト増や歩留まり低下を解決し、多様なニーズに対応できる点で注目されています。
CPUやGPU、メモリなどを独立したチップレットとして組み合わせることで、高性能で効率的な半導体デバイスを実現します。
チップレットが注目される理由|半導体微細化の限界を打破
従来の半導体製造では、一つのチップに全ての機能を組み込むモノリシックな方法が主流でした。しかし、この方法では半導体の微細化が物理的、経済的な限界に達しつつあり、ムーアの法則の維持が困難になっています。特に、2nmプロセスのような最先端技術においては、製造コストの増大や歩留まりの低下が顕著になる点が課題です。チップレット技術は、この課題を打破する新しいアプローチとして注目されています。機能ごとに分割された小さなチップ(チップレット)を複数組み合わせることで、大きなチップを製造する際の欠陥リスクを低減し、歩留まりの向上を図れます。これにより、開発コストを抑えつつ、高性能な半導体を効率的に生産できるのです。例えば、ローチとネルが提唱したように、個々のチップレットを最適なプロセスで製造し、それらを統合することで、全体の性能とコストのバランスを最適化できます。
チップレット技術がもたらす4つのメリット
チップレット技術は、半導体業界において注目されている新たなアプローチであり、多くのメリットと利点をもたらします。まず、機能や製造プロセスの異なる複数の小さなチップを自由に組み合わせることで、特定の用途に最適化された半導体を柔軟に構築できる点が大きなメリットです。これにより、アナログ回路とデジタル回路など、異なる特性を持つチップを最適なプロセスで製造し、それらを統合することが可能となります。
さらに、チップレット技術は不良品率の低減にも寄与します。大きな単一チップの製造では、一部に欠陥が発生するとチップ全体が不良品となるリスクがありましたが、小さなチップレットに分割することで、欠陥の影響を受ける確率が低減され、全体の歩留まりが向上します。 この結果、生産効率が改善され、製造コストの削減にもつながります。また、既存の信頼性の高いチップを再利用することで、開発期間の短縮にも貢献します。
メリット1:異なる機能のチップを自由に組み合わせられる
チップレット技術の最大のメリットは、異なる機能を持つチップを自由に組み合わせて、一つの大規模な半導体として機能させられる点です。これは、ヘテロジニアスインテグレーション(異種チップ集積)と呼ばれる技術で、製造プロセスや機能の違うチップレットを、まるでブロックのように組み合わせてパッケージに収めることを可能にします。
従来のSoC(System on Chip)では、CPUやメモリ、I/Oといった複数の機能をすべて一つのチップに集積していたため、すべての回路を最先端の微細加工技術で製造する必要がありました。しかし、DRAMやフラッシュメモリ、RF回路など、ロジック回路とは異なる製造技術が適しているものや、最先端の技術を使わなくても十分な性能を発揮できる機能も存在します。これらの違いを考慮せずにすべてを最先端で製造すると、コスト増加や歩留まりの低下につながる可能性がありました。
チップレットでは、機能ごとに最適なプロセスで製造されたIP(知的財産)ブロックであるチップレットを選び、それらを組み合わせることで、高性能化、多機能化、低コスト化を実現できます。これにより、MCM(マルチチップモジュール)やSiP(システムインパッケージ)のように、異なる機能を持つ複数のチップを一つのパッケージに統合するアプローチがさらに進化し、設計の自由度が格段に向上するのです。
メリット2:不良品率を下げて生産効率(歩留まり)を改善
チップレット技術は、半導体製造における不良品率の低減に大きく貢献し、生産効率(歩留まり)を改善します。従来のモノリシックICでは、全ての機能を一つの大きなチップに集積するため、わずかな欠陥でもチップ全体が不良品となっていました。例えば、製造プロセスにおいて10mm四方のチップで歩留まりが50%だった場合、20mm四方のチップでは歩留まりが約6.25%にまで低下する可能性があります。これは、チップサイズが大きくなるほど欠陥の影響を受けやすくなるためです。チップレットでは、機能を分割して複数の小さなチップにすることで、個々のチップの製造が容易になり、結果として不良品となるリスクを軽減できます。これにより、全体の歩留まりが向上し、製造コストの削減にもつながります。特に、高性能な半導体や大型の半導体を製造する際に、このメリットは顕著に現れます。
メリット3:開発期間の短縮と製造コストの削減を実現
チップレット技術は、半導体メーカーにとって開発期間の短縮と製造コストの削減という大きなメリットをもたらします。従来のモノリシックICでは、機能を追加するたびにチップ全体を再設計する必要があり、これには膨大な時間とコストがかかっていました。しかし、チップレットを活用することで、必要な機能を持つチップレットを複数組み合わせるだけで新たな半導体を構築できるため、開発プロセスを大幅に効率化できます。これにより、各機能の設計を独立して進められるため、開発期間を短縮できます。
また、チップレットは製造コストの削減にも貢献します。例えば、特定機能の性能を向上させたい場合、モノリシックICでは全体を微細化しなければなりませんが、チップレットであればその機能を持つチップレットだけを微細化すれば済みます。これにより、高価な最先端プロセスを必要な部分だけに適用できるため、全体のコストを抑えることが可能です。さらに、機能ごとに最適なプロセスを選択できるため、製造歩留まりの向上にもつながり、結果として全体的な製造コストの削減を実現します。
このモジュール化されたアプローチは、新しい半導体製品を市場に投入するまでの時間を大幅に短縮し、競争力の強化にも寄与するでしょう。
メリット4:柔軟な設計で多様なニーズに対応可能に
チップレット技術の大きなメリットは、特定の用途や要件に最適化された半導体製品を構築できる柔軟性にあります。複数の小さなチップ(チップレット)を組み合わせることで、顧客の多様なニーズにきめ細かく対応することが可能です。例えば、高性能コンピューティング向けの製品では最先端のプロセス技術を用いたチップレットを組み合わせ、IoTデバイス向けの製品では低消費電力に特化したチップレットを使用するといった柔軟な設計が可能になります。
これにより、自動車メーカーが自動運転用の高性能AI半導体と機能安全部品を制御するマイコンを組み合わせるように、特定の機能を持つチップレットを自由に選択し、システムのカスタマイズ性を高めることができます。 複数のチップレットを組み合わせることで、顧客の要求に応じてSoC(System on Chip)を短期間でカスタマイズできるため、開発期間の短縮にも繋がります。 また、ASIC(特定用途向け集積回路)のようなカスタム製品においても、チップレットを活用することで開発コストと時間を削減し、市場投入までのスピードを向上させることが期待されています。 この柔軟な設計アプローチは、AIや通信など幅広い分野で技術革新を促進し、今後の半導体産業を支える重要なキーテクノロジーとして注目されています。
チップレット導入における3つの課題(デメリット)
チップレットの導入には、いくつかのデメリットと課題が存在します。まず、複数のチップを統合するパッケージング工程が複雑になり、製造コストの上昇を招く可能性があります。特に、インターポーザと呼ばれるチップレット間を接続する基板の性能や精密な配線には、専用の設備と高度な技術が不可欠です。次に、チップレット間の高速なデータ通信技術が不可欠となりますが、電力消費の増加や発熱、ノイズといった新たな課題も生じやすく、これらを抑制するための精密な制御技術や冷却システムの導入が求められます。最後に、複数のチップを組み合わせることで、全体の設計や検証が複雑になるデメリットがあります。特に、各チップレット間の相互通信やデータ処理の正確性を確認するためには、高度な検証技術やツールの活用が必須です。
課題1:チップ間の高速なデータ通信技術が不可欠
チップレット技術において最も重要な課題の一つは、個々のチップレット間でいかに高速かつ効率的にデータ通信を行うかという点です。従来のモノリシックな半導体では、チップ内部の回路が直接接続されていたため、高速な通信が可能でした。しかし、チップレットは複数の小さなチップを組み合わせるため、それらを接続するインターフェースを介した通信が必須となります。この通信速度が全体の性能を左右するため、インターコネクト技術の進化が不可欠です。例えば、シリコンインターポーザーや、2.5D/3Dパッケージングといった技術がこの課題解決に貢献すると期待されています。これらの技術は、チップレット間の物理的な距離を縮め、より高密度な接続を可能にすることで、高速な通信を実現します。また、通信速度だけでなく、消費電力の低減も重要な課題です。高速な通信は一般的に多くの電力を消費するため、低消費電力でありながら高速な通信を実現する接続方法の開発が求められています。これにより、チップレット全体の性能向上と、省エネルギー化を両立させることが可能になります。
課題2:複数のチップを統合する設計・検証が複雑化
チップレット技術では、複数の異なる機能を担う小さなチップを組み合わせて一つのパッケージにするため、個々のチップレットの設計と検証だけでなく、それらを統合した全体の動作確認が非常に複雑になります。具体的には、各チップレット間の高速なデータ通信や、電力供給、熱管理、ノイズ対策といった多岐にわたる課題を考慮した設計が求められるため、モノリシックな単一チップに比べて設計プロセス全体が複雑化する傾向にあります。
この複雑な設計と検証に対応するためには、エレクトロニック・デザイン・オートメーション(eda)ツールの高度化が不可欠です。edaツールは、設計の自動化、シミュレーション、物理設計、そして複数のチップレットが連携する際の相互接続やデータ処理の正確性を確認する統合検証において重要な役割を果たします。 例えば、チップ間インターコネクトの設計や電源分配、クロック同期、キャッシュコヒーレンシなどの要素は、モノリシックな設計よりも複雑なため、edaツールのサポートが不可欠です。 また、複数のベンダーから提供されるIP(Intellectual Property)を相互接続する場合、UCIe(Universal Chiplet Interconnect Express)のような共通規格が整備されても、実際の動作確認やデバッグには膨大なテスト工数が必要になることがあります。
このように、チップレットの統合設計は、高度な技術と専門知識を要し、edaツールの進化と設計プロセスのさらなる自動化が今後の普及のカギを握っています。
課題3:高度な実装(パッケージング)技術が求められる
チップレット技術の導入には、高度な実装(パッケージング)技術が不可欠です。半導体の製造工程は、シリコンウェハーを製造する「中工程」と、そのウェハー上に半導体チップを作り込む「前工程」、そしてチップを切り出してパッケージ化する「後工程」に大別されますが、チップレット技術は特に後工程における革新を促しています。
複数のチップレットを一つのパッケージに収めるには、従来の単一チップ型SoC(System on Chip)よりも複雑なパッケージングが必要となり、製造コストの増加につながる可能性があります。
特に、チップレット間の高速なデータ通信と電力供給を可能にするためには、精密な接続と配線技術が求められます。この課題に対応するため、インターポーザと呼ばれる配線専用の中間基板が重要な役割を果たします。インターポーザには、シリコン、有機ポリマー、ガラスなどが利用され、高密度な配線を実現し、チップ間の信号伝達を効率化します。
また、チップレットを縦方向に積層する3次元実装技術も注目されています。これにより、実装面積の削減とチップ間の接続距離短縮が可能になりますが、積層によって熱が集中しやすくなるため、高度な熱管理技術が不可欠です。 FOWLP(Fan-Out Wafer Level Package)のような先端パッケージング技術は、このような高密度な実装と熱問題の解決に貢献しており、複数のチップレットを効率的に統合するための精密な接続や配線を可能にします。 チップレット技術の進展に伴い、これらの実装技術は半導体製造の新たな競争軸として重要性を増しているのです。
チップレットの最新動向と今後の展望
チップレット技術は、半導体業界の新たな潮流として、世界的な開発競争が繰り広げられています。特に、データセンター、クラウドコンピューティング、生成AIといった高性能な処理能力を要求される分野において、チップレットの需要は高まっています。この技術は、2023年にいくつかの重要なブレークスルーを見せ、今後はSystem on Chip(SoC)設計からチップレット方式への移行が加速すると予測されています。
Yole Groupは、2027年までにチップレットベースのプロセッサ市場が1,350億米ドルを超えると予測しています。また、同社は2032年にはチップレット採用がコンシューマーおよび自動車市場で加速し、防衛、航空宇宙、産業、医療分野でも足がかりを得て、チップレットベースICのTAM(Total Addressable Market)が2,050億米ドルを超えると予測しています。この成長は、AIや機械学習、高性能コンピューティングアプリケーションの需要増加に牽引されており、チップレットがこれらの分野で柔軟かつスケーラブルなソリューションを提供できるためです。また、UCIe(Universal Chiplet Interconnect Express)のような標準化への取り組みも進んでおり、異なるベンダーのチップレット間の相互運用性を促進し、さらなる市場拡大に貢献しています。
世界的な開発競争と標準化に向けた取り組み
チップレット技術は、半導体の性能向上とコスト削減を両立させるために、世界中の企業やメーカーが開発競争を繰り広げています。特に、異なるメーカーのチップレットを自由に組み合わせて利用するための標準化が重要な課題です。この課題を解決するために、様々なコンソーシアムが設立され、標準仕様の策定が進められています。
代表的な例としては、インテル、AMD、Arm、Google、Microsoft、Samsung、TSMCといった主要な半導体メーカーやIT企業が参加するUniversal Chiplet Interconnect Express(UCIe)コンソーシアムが挙げられます。UCIeは、ダイ間の物理I/O層やプロトコル、ソフトウェアスタックの標準仕様「UCIe 1.0」を発表し、チップレットエコシステムの構築を目指しています。2024年8月には、UCIe 2.0仕様がリリースされ、チップレット間の接続仕様がさらに整備されました。 また、Armはチップレットシステムアーキテクチャ(CSA)の仕様を公開し、60以上の企業が参加して標準化を促進しています。
日本でも、この世界的な開発競争に積極的に参加しています。例えば、東京工業大学などが「チップレット集積プラットフォーム・コンソーシアム」を設立し、アルバックや住友ベークライトといった日本の企業がメンバーとして研究を進めています。 また、自動車分野では、自動車用先端SoC技術研究組合(ASRA)が設立され、自動車メーカーを軸に、チップレット技術を用いた車載半導体の研究開発と仕様共通化に取り組んでいます。 これらの取り組みは、各企業の研究や論文発表、技術ロードマップにも反映され、チップレット技術のさらなる進化と普及に向けた基盤を築いています。
さらなる性能向上を支えるパッケージング技術の進化
チップレット技術の進化を支える上で、半導体パッケージング技術は非常に重要な役割を担っています。従来の半導体製造は微細化が中心でしたが、その技術的・経済的限界が近づくにつれて、後工程におけるパッケージング技術の革新が不可欠となりました。現在、チップレットを一つのパッケージに統合するため、多種多様なパッケージング技術が開発されています。
具体的には、チップレットを水平方向に接続する2.5次元(2.5D)パッケージングや、垂直方向に積層して高集積化を実現する3次元(3D)パッケージングが主流です。これらの技術では、チップレット間の高速データ通信を可能にするために、マイクロバンプ接続やスルーシリコンビア(TSV)、シリコンインターポーザーといった技術が活用されています。
また、ファンアウト・ウェハーレベル・パッケージング(FOWLP)などの技術も、配線密度を高め電気特性を向上させるために導入されています。
インテルやAMD、NVIDIA、サムスン、IBM、ソシオネクスト、ルネサスなどの半導体メーカー各社は、ASEやTELといったOSAT(Outsourced Semiconductor Assembly and Test)企業と連携しながら、これらの先端パッケージング技術の開発競争を繰り広げています。さらに、異なる材料のチップレットを組み合わせるヘテロインテグレーション技術も進化しており、高熱伝導性樹脂や低応力樹脂、薄型封止技術など、新しい材料や構造の導入も進んでいます。これにより、チップレット技術は、AIやデータセンター、自動運転などの多様な分野での応用拡大を支える中核技術として、その重要性を増しています。
AIやデータセンターなど多様な分野への応用拡大
チップレット技術は、AIの進化とデータセンターの需要増加に対応する上で非常に重要な用途が期待されています。特に、AIデータセンターでは電力効率やコストが課題となっており、チップレット集積の採用が現実的な解決策だと考えられています。例えば、大規模なAIクラスターでは、プロセッサやメモリ、ストレージ間のデータフローを処理するために膨大なネットワークインフラが必要ですが、チップレットはシステムの消費電力量を25〜50%削減できる可能性を秘めています。
また、チップレットは、高性能コンピューティング(HPC)やAIチップの構築において、歩留まりを最適化しつつ、先端プロセスを活用した高性能半導体チップを実現できるため、GPU、CPU、ASICなどでの採用が増加しています。AMDは高性能CPUのRyzenやサーバー用CPUのEpycでチップレットを積極的に採用しており、AppleもArmベースの高性能チップにチップレット技術を応用していると考えられます。QualcommやNVIDIAなどの企業も、AI向けチップやデータセンター向け製品でのチップレット技術活用に注力しています。
さらに、チップレットはスマホや車載システムといった多様な分野への応用も拡大しています。自動車の先進運転支援システム(ADAS)や次世代RF接続アプリケーションなど、高性能かつ低消費電力のソリューションが求められる領域で、チップレット設計の加速が進められています。
まとめ
チップレット技術は、半導体の微細化が限界に近づく中で、新たな進化を促す革新的なアプローチとして注目されています。この技術は、CPUやGPUなどの異なる機能を持つ複数の小さなチップ(チップレット)を組み合わせて一つのパッケージにすることで、半導体の性能向上、コスト削減、開発期間の短縮、そして柔軟な設計を実現します。
しかし、チップレットの導入には、チップ間の高速データ通信や複雑な設計・検証、高度なパッケージング技術が不可欠であるという課題も存在します。
現在、世界中で開発競争が進み、標準化に向けた取り組みが活発化しています。特にAIやデータセンターなどの分野では、チップレット技術の応用が拡大しており、今後の半導体業界において重要な役割を担うと期待されています。

西進商事コラム編集部
西進商事コラム編集部です。専門商社かつメーカーとしての長い歴史を持ち、精密装置やレーザー加工の最前線を発信。分析標準物質の活用も含め、さまざまなコラム発信をします。
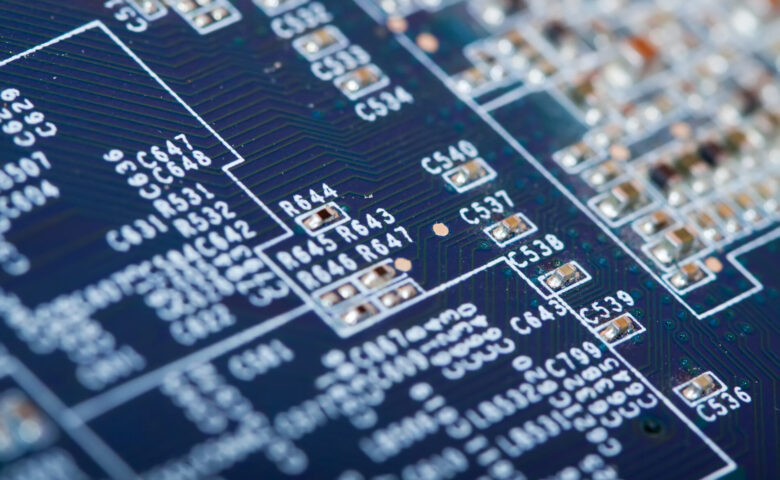
アングストローム技術とは?オングストローム時代の半導体の仕組み
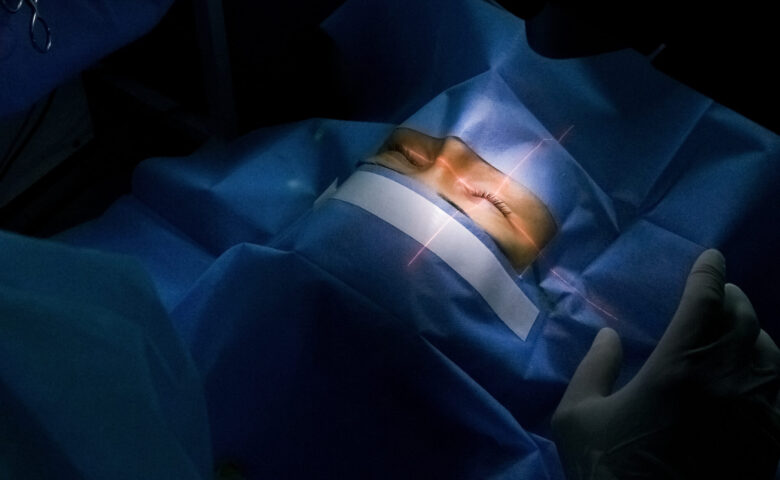
エキシマレーザとは?用途や特徴・仕組みについて解説

yag(ヤグ)レーザとは?仕組みや特徴・用途を説明