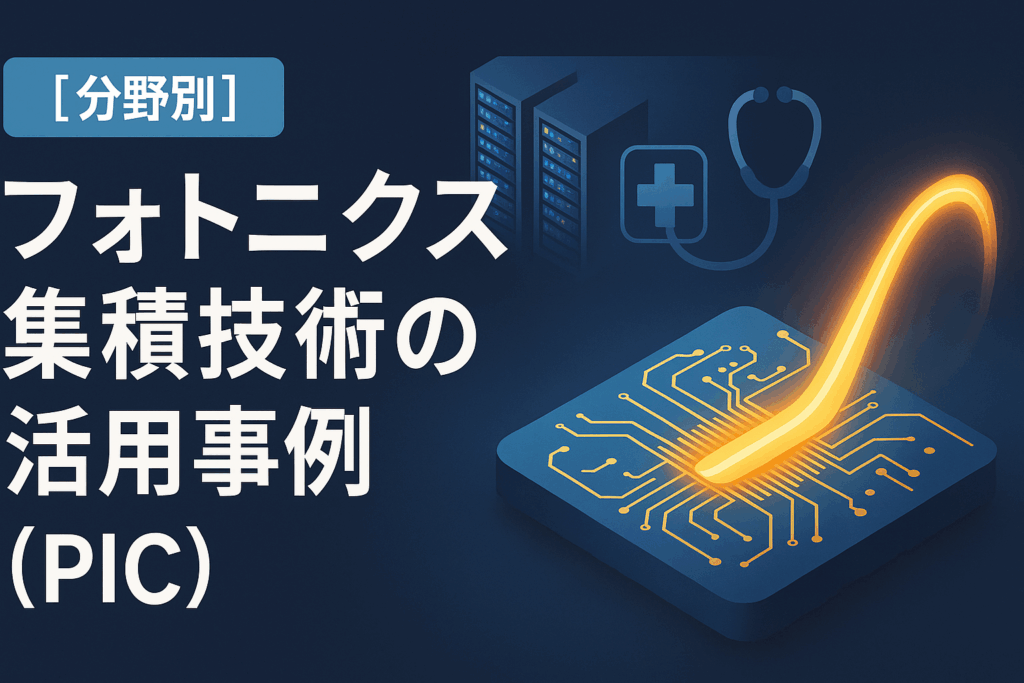
- INDEX目次
目次【非表示】
- 1.フォトニクス集積の基本:光の技術を半導体チップに凝縮
- 2.フォトニクス集積がもたらす3つの大きなメリット
- 2-1.メリット1:機器の大幅な小型化を実現できる
- 2-2.メリット2:データ伝送の高速化と大容量化を両立する
- 2-3.メリット3:消費電力を抑えて環境負荷を低減する
- 3.フォトニクス集積は従来の光学部品と何が違うのか
- 3-1.違い1:部品点数を削減し製造コストを抑えられる
- 3-2.違い2:半導体技術による大量生産が可能になる
- 4.【分野別】フォトニクス集積技術の活用事例
- 4-1.事例1:データセンターにおける通信インフラの高速化
- 4-2.事例3:医療分野での精密な検査・診断技術への貢献
- 5.フォトニクス集積技術を導入するまでの流れ
- 6.用語解説
- 7.まとめ
フォトニクス集積(PIC)とは、光の性質を制御・活用する技術である「フォトニクス」を、半導体集積回路の製造技術と融合させることで、光回路を小型のチップ上に組み込む技術です。これまで別々の部品として扱われていた光部品を一つのチップ上に集積することで、光信号の生成・伝送・検出などを効率的に行えます。この技術は、データ通信における高速化や大容量化、さらには省電力化を実現する鍵として注目されています。
本記事ではフォトニクス集積の解説をするとともに、関連する用語も解説しています。(記事最後参照)
フォトニクス集積の基本:光の技術を半導体チップに凝縮
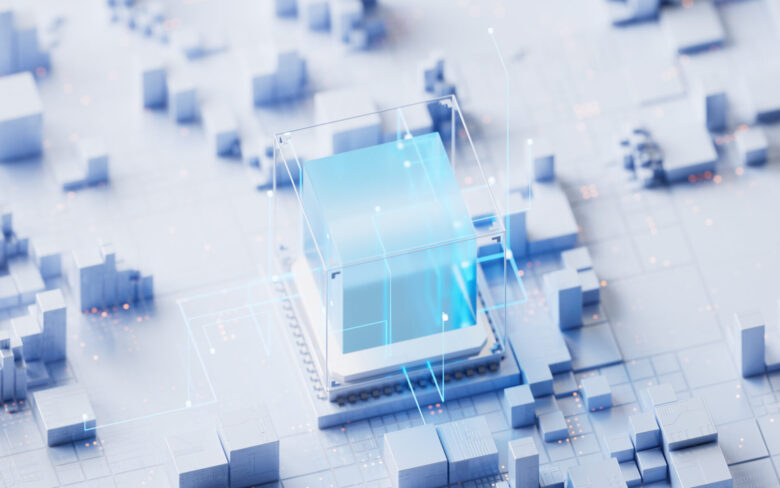
フォトニクス集積とは、光の技術を半導体チップに凝縮する画期的な技術です。従来の電子回路が電子で情報を伝達するのに対し、フォトニクス集積回路(PIC)は光子を利用して情報を生成、伝送、変調、計測します。これにより、光通信で不可欠な多様な機能を一つのチップ上に集約することが可能になります。
特に、シリコンフォトニクスは、半導体の主要材料であるシリコン基板上に光回路を構築する技術であり、LSI製造と同じ微細加工技術を応用できるため、デバイスの小型化、省エネルギー化、そして大量生産によるコスト削減が期待されています。
フォトニクスの基礎は、光の波長や物理現象を材料開発やデバイス設計に応用することにあり、これにより高速伝送や低消費電力化が実現されます。この技術は、情報通信、医療、車載システム、さらには量子コンピューティングなど、幅広い分野での応用が期待されています。
フォトニクス集積がもたらす3つの大きなメリット
フォトニクス集積は、複数の光学部品を一つのマイクロチップ上にまとめるため、光信号の生成、伝送、変調、検出といった多様な機能をコンパクトなデバイスで実現できます。この技術は特に通信分野において、機器の大幅な小型化、データ伝送の高速化と大容量化、そして消費電力の低減という3つの大きなメリットをもたらします。各メリットについて詳しく見ていきましょう。
メリット1:機器の大幅な小型化を実現できる
フォトニクス集積(PIC)は、複数の光学部品を半導体チップ上に一体化する技術であり、機器の小型化に大きく貢献します。従来の光学部品は個々に大きく、筐体上に配置して接続する必要がありましたが、フォトニクス集積ではこれらの部品を単一のチップに集約できるため、大幅な小型化が実現します。例えば、インテル社はシリコンフォトニクス技術を用いて、従来の光変調器を1000分の1に小型化することに成功しました。
また、OKIはシリコンフォトニクス技術を活用して超小型の光集積回路チップを開発し、光ファイバーセンサーやレーザー振動計、光バイオセンサーといった多様な光センサーの適用領域を拡大しています。 この技術は、LSI(大規模集積回路)のような超小型化と低消費電力化、そして大量生産による低コスト化を可能にし、これまで大型で高価だった光センサーをスマートフォンやタブレットのようなサイズ感で実現できるようになります。 これにより、光センサーの利用範囲が飛躍的に広がり、社会インフラの老朽化対策や環境問題への貢献も期待されています。
メリット2:データ伝送の高速化と大容量化を両立する
フォトニクス集積は、データ伝送の高速化と大容量化を両立させる画期的な技術です。従来の電気信号による通信では、伝送速度や帯域幅に限界があり、高速通信を実現するためには多くのエネルギーを消費するという課題がありました。しかし、光を用いたフォトニクス集積では、これらの課題を克服できます。光は電気に比べてはるかに高速で情報を伝えられ、また、一本の光ファイバーに複数の異なる波長の光信号を束ねる「波長多重」という技術を用いることで、飛躍的に伝送容量を増大させることが可能です。
例えば、富士通研究所ではCPU間の大容量データ伝送に向けて、4波長シリコン集積レーザーを開発しました。これにより、1本の光ファイバーでより多くの波長の信号を伝送できるようになり、毎秒数テラビットに及ぶデータを入出力するスーパーコンピューターやハイエンドサーバーでの応用が期待されています。
また、産総研はシリコンフォトニクス光スイッチを用いて、1.25億ギガビット毎秒という世界最大容量の光スイッチネットワークを達成できることを示しました。これはブルーレイディスク約60万枚以上の情報を1秒間に伝送できる容量に相当し、次世代の大規模データセンターやスーパーコンピューターの高性能化・省電力化に貢献すると考えられています。
このように、フォトニクス集積技術は、情報通信におけるデータ伝送のボトルネックを解消し、より高速かつ大容量な通信環境を実現する上で不可欠な存在となっています。
メリット3:消費電力を抑えて環境負荷を低減する
フォトニクス集積回路(PIC)は、従来の電子回路と比較して消費電力を大幅に削減できます。特に、データセンターや通信ネットワークにおいては、データ量の増大に伴い消費電力の増加が課題となっており、PICの導入がその解決策として注目されています。電子回路では電気信号を伝送する際に抵抗によるジュール熱が必ず発生し、これが電力消費の大きな要因となります。さらに、配線が長くなると信号を増幅し直す必要があり、これも電力負荷を増やします。
一方で、PICは電気ではなく光信号(光子)を用いるため、信号伝送における抵抗損失や熱損失を最小限に抑えられます。光は電気に比べて劣化が少なく、長距離でも中継や増幅の回数を大幅に減らせるほか、波長多重(複数の波長を同時に利用)によって同じエネルギーで大量のデータを一度に運べるため、エネルギー効率が飛躍的に高まります。
例えば、人工知能(AI)の学習やビッグデータ解析など、膨大なデータを高速で処理する現代のコンピューティング環境では、半導体デバイスの電力効率が非常に重要になります。PICは、これらの分野において、より少ない電力で高性能なデータ処理を実現し、結果としてCO2排出量の削減にも貢献します。このように、フォトニクス集積は、環境負荷の低減と持続可能な社会の実現に不可欠な技術として、その役割をますます拡大しています。
フォトニクス集積は従来の光学部品と何が違うのか
フォトニクス集積は、複数の光学部品を一つの半導体チップ上に集約する技術であり、フォトニクスの基礎となる光の特性を最大限に活用します。従来の光学部品は、個々の素子を組み合わせて光学ユニットを構成するため、システムが複雑で大型化しやすく、精密な組み立て作業が不可欠でした。一方、フォトニクス集積では、光信号の生成・伝送・変調・計測など多様な機能をワンチップに統合することで、大幅な小型化、軽量化、省電力化を実現できます。また、半導体製造技術を応用できるため、大量生産によるコスト削減や安定した性能が期待できる点も大きな違いです。
違い1:部品点数を削減し製造コストを抑えられる
フォトニクス集積は、複数の光回路を単一の半導体チップ上に集約する技術です。この集積により、個別の光学部品を組み立てる必要がなくなるため、部品点数を大幅に削減し、製造コストを抑えることが可能になります。具体的には、光の変調器、導波路、検出器などを半導体製造プロセスであるCMOSプロセスを応用してチップ上に作り込むことで、低コストでの大量生産が期待できます。
従来の光学部品は、一つひとつの部品を精密に位置合わせして組み立てる必要があり、この工程は時間とコストがかかるだけでなく、複雑なシステムになるほど接続部の損失や故障のリスクも増大する傾向がありました。しかし、フォトニクス集積では、これらの光機能を半導体チップ内部で直接結合するため、部品間の接続が不要となり、組み立て工程が簡素化されます。
この簡素化は、製造時間の短縮だけでなく、歩留まりの向上にも貢献し、結果として全体の製造コストを大幅に引き下げます。特にデータセンターやAIネットワークのように、大量の光トランシーバーを必要とする分野では、フォトニクス集積によるコスト削減効果は非常に大きく、広く普及するための重要な要因となっています。
違い2:半導体技術による大量生産が可能になる
フォトニクス集積は、半導体チップ上に光回路を形成する技術であり、従来の光学部品とは異なり、半導体技術を活用した大量生産が可能です。従来の光学部品は、レンズやミラーなどの複数の部品を組み合わせて製造されるため、製造工程が複雑でコストも高くなりがちでした。また、部品ごとに調整が必要なため、生産効率も低いという課題がありました。
これに対し、フォトニクス集積では、半導体製造で培われた微細加工技術を応用することで、光回路をチップ上に一体形成できます。具体的には、シリコンや化合物半導体などの基板上に、光を導くための導波路や変調器、検出器といった光デバイスを、半導体集積回路と同様のプロセスで作り込みます。これにより、高精度な光学部品を、半導体チップと同様に一度に大量生産することが可能になります。例えば、シリコンフォトニクスと呼ばれる技術では、既存のCMOS製造プロセスを利用して、光回路を安価かつ大量に生産できる点が大きなメリットです。この製造方法の確立によって、フォトニクス集積技術の普及が加速し、さまざまな分野での応用が期待されています。
【分野別】フォトニクス集積技術の活用事例
フォトニクス集積技術は、さまざまな分野で革新的なソリューションを提供しています。ここでは3つの例をご紹介します。
事例1:データセンターにおける通信インフラの高速化

動画コンテンツの利用拡大やリモートワークの普及、さらに生成AIや自動運転システムの発展に伴い、データ通信量が爆発的に増加しています。この膨大なデータ通信を支えるデータセンターでは、数千台規模のサーバーやネットワーク機器が稼働しており、大量の電力消費が課題となっています。国内外でカーボンニュートラルへの関心が高まる中、データセンターのグリーン化、つまり環境負荷の低減が喫緊の課題です。
この課題を解決する鍵として注目されているのが、光電融合技術を用いたフォトニクス集積回路(PIC)です。PICは、電気信号を扱う回路と光信号を扱う回路を融合させる技術であり、従来の電子回路と比較して、通信の高速化と低消費電力化を同時に実現します。
具体的には、プロセッサと光I/O(シリコンフォトニクスチップ)を同一パッケージ内に配置するCPO(Co-Packaged Optics)技術により、電気信号の移動距離を短縮し、信号劣化や電力消費を大幅に削減できます。これにより、データセンター内の通信速度を飛躍的に向上させつつ、消費電力を大幅に削減することが可能です。
例えば、日立ハイテクグループのVLCフォトニクス社は、次世代高速データセンター向けに高速変調用光集積回路の技術開発を進めています。また、STMicroelectronicsが主導するSTARLightコンソーシアムは、最大200Gb/sを処理するデータセンター向けデータ通信デモンストレーターの構築を目標としています。これらの取り組みにより、2030年までに現在の約40%低消費電力で高性能なデータセンターが実現すると予測されています。
フォトニクス集積技術は、データセンターの高速化、大容量化、そして省エネルギー化に貢献し、次世代のデジタルインフラを支える基盤技術として期待されています。
事例3:医療分野での精密な検査・診断技術への貢献

医療分野において、フォトニクス集積技術は検査・診断の精度向上に大きく貢献しています。この技術は、光の特性を利用してさまざまな光学コンポーネントを一つの半導体チップに集積することで、従来の大型で高価だった医療機器の小型化と高性能化を可能にします。例えば、OCT(光コヒーレンストモグラフィー)のような画像診断装置は、フォトニクス集積回路の適用により、手持ちサイズにまで小型化できる可能性があります。これにより、より多くの医療現場で手軽に高度な検査が行えるようになり、早期診断や病状の正確な把握に役立ちます。
また、フォトニクス集積技術は、血圧や血糖値などの生体情報をリアルタイムでモニタリングするウェアラブルデバイスへの応用も期待されています。複数のパラメーターに基づいた高精度な診断デバイスや、DNAシーケンシングの高速化・低コスト化にも貢献し、よりパーソナルな医療の実現を後押しするでしょう。
半導体製造技術の進歩と組み合わせることで、フォトニック集積回路は高い信頼性と安定性を持ちながら大量生産が可能となり、医療機器のコスト削減にもつながります。シリコンフォトニクスは特にこの分野で注目されており、光ファイバーセンサーや光バイオセンサーなど、多様な光センサーの超小型化・低消費電力化・低コスト化を実現する超小型光集積回路チップの開発も進められています。
フォトニクス集積技術を導入するまでの流れ
フォトニクス集積技術を導入するまでには、いくつかのステップがあります。まず、フォトニクスの基礎となる光波の性質や光学素子について理解することが重要です。その上で、具体的な用途や事業に、光集積回路化が適しているかを調査・検討します。次に、光学システムの仕様に基づいたエンジニアリングスタディを行い、集積回路の設計へと進みます。フォトニック集積回路(PIC)の設計には、光子の挙動や材料との相互作用、信号の変調に関わる複雑な物理学の知識が必要となるため、シミュレーションツールを活用することで、設計の性能や堅牢性を最適化できます。設計後は、ファウンドリと呼ばれる製造拠点との連携により、チップ製造プロセスへと移行します。この一連の流れを経て、フォトニクス集積技術が導入されるのです。
用語解説
フォトニクス (Photonics)
光(光子)の性質を制御・利用する技術や学問分野のこと。光通信、レーザー、光センサーなど広範囲に応用される。
光子 (Photon)
光の最小単位の粒子。量子力学的に振る舞い、波の性質と粒の性質の両方をもつ。
フォトニクス集積回路(PIC: Photonic Integrated Circuit)
光を使う回路を、半導体チップ上に集積したもの。電子回路の「光版」と考えるとイメージしやすい。
シリコンフォトニクス (Silicon Photonics)
シリコン基板上に光回路を形成する技術。半導体製造のノウハウ(CMOSプロセスなど)を使えるため、量産やコスト低減に強い。
LSI(Large Scale Integration、大規模集積回路)
大量のトランジスタを1枚のチップに集積した回路。PCやスマホのCPUなどが典型例。
CMOSプロセス (Complementary Metal-Oxide-Semiconductor process)
半導体回路を作るための製造技術。低消費電力で高性能なICを大量生産できるのが特徴。
波長多重(WDM: Wavelength Division Multiplexing)
1本の光ファイバーに複数の異なる波長(色)の光信号を同時に流して、大容量の通信を実現する技術。
CPO(Co-Packaged Optics)
プロセッサと光入出力(光I/O)を同じパッケージに収める技術。信号劣化や消費電力を減らせる。
LiDAR(Light Detection and Ranging)
レーザー光を照射して反射を計測し、周囲の距離や形状を把握するセンサー。自動運転車の「目」にあたる。
OCT(Optical Coherence Tomography:光コヒーレンストモグラフィー)
光の干渉を利用して体内を断層イメージ化する医療診断技術。眼科や循環器科でよく使われる。
ファウンドリ(Foundry)
半導体チップを設計ではなく製造だけを請け負う工場や企業。設計会社から依頼を受けて製造を担当する。
まとめ
フォトニクスとは、光の生成、制御、検出などを扱う多分野にわたる研究領域です。光の粒子である光子を用いて、光の力と速度を活用した実用的なアプリケーションの設計に役立てられています。このフォトニクス技術を半導体チップに凝縮したものがフォトニクス集積であり、光を生成・伝送・変調・計測する回路を形成します。電子集積回路が電子を使うのに対し、フォトニック集積回路は光子を使用するという点が大きな違いです。
フォトニクス集積は、データ伝送の高速化と大容量化、機器の小型化、消費電力の削減といった多くのメリットをもたらします。これにより、データセンターの通信インフラ、自動運転センサー、医療分野での精密検査など、幅広い分野での活用が期待されています。

西進商事コラム編集部
西進商事コラム編集部です。専門商社かつメーカーとしての長い歴史を持ち、精密装置やレーザー加工の最前線を発信。分析標準物質の活用も含め、さまざまなコラム発信をします。
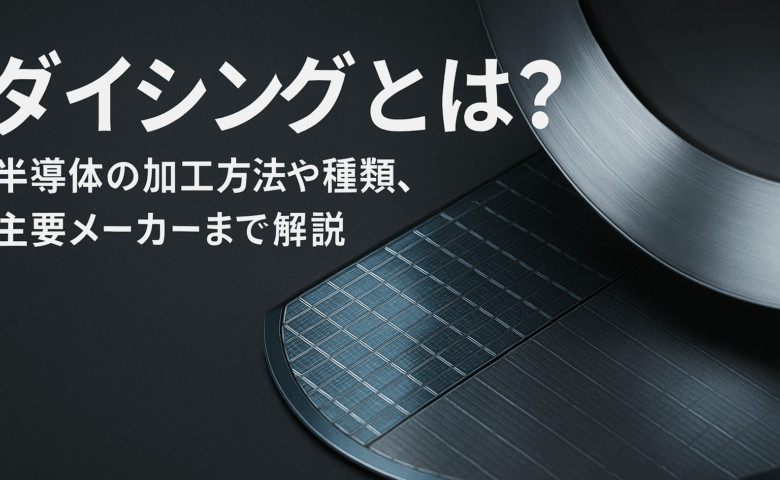
ダイシングとは?半導体の加工方法や種類、主要メーカーまで解説
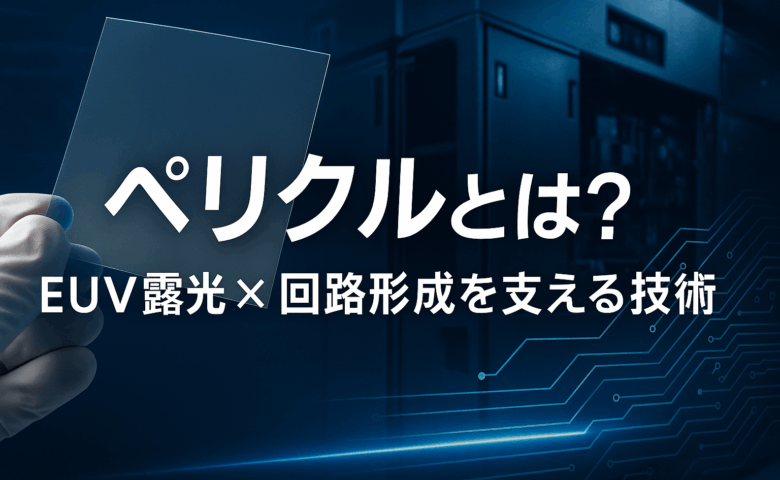
ペリクルとは?半導体のEUV露光・回路形成を支える機能と主要会社を解説

