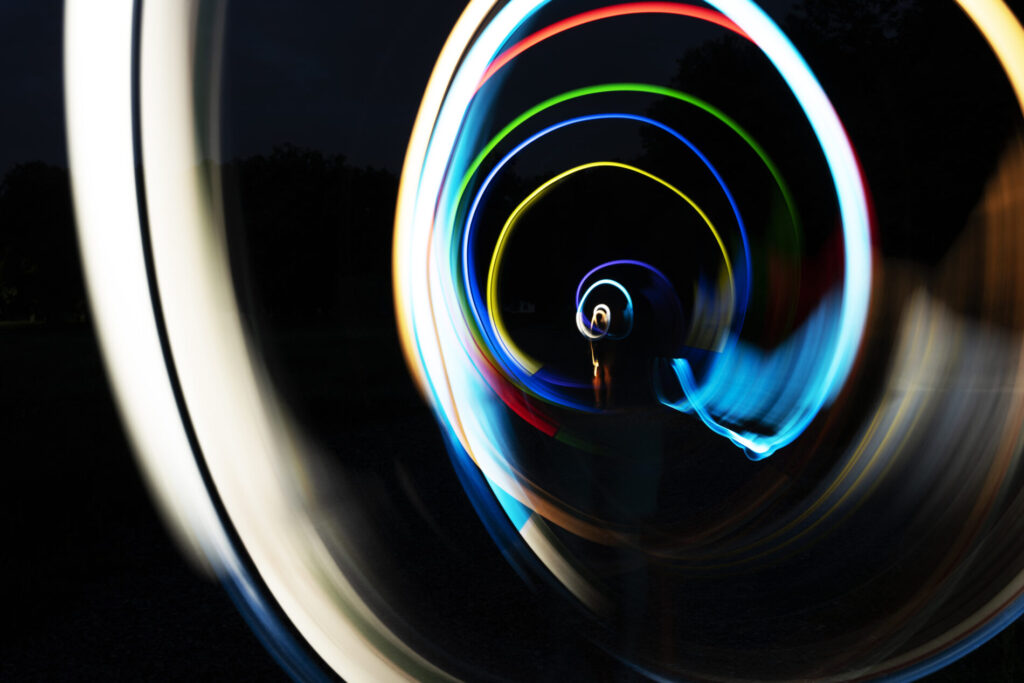
- INDEX目次
目次【非表示】
- 1.リソグラフィー技術とは半導体製造に不可欠な微細加工技術
- 2.写真の原理を応用したフォトリソグラフィの仕組み
- 3.半導体回路を形成するフォトリソグラフィの8つの主要工程
- 3-1.①前処理:ウェーハ表面を洗浄し密着性を高める
- 3-2.②レジスト塗布:感光材(フォトレジスト)を均一に塗る
- 3-3.③プリベーク:塗布したレジストを加熱し乾燥させる
- 3-4.④露光:マスクを通して回路パターンを光で焼き付ける
- 3-5.⑤現像:不要になったレジストを薬品で溶かして除去する
- 3-6.⑥ポストベーク:現像後のレジストパターンを硬化させ安定させる
- 3-7.⑦エッチング:レジストをマスクにして膜を削り回路を彫る
- 3-8.⑧レジスト剥離:役目を終えたレジストを取り除く
- 4.なぜリソグラフィーは重要?半導体の性能を左右する微細化の鍵
- 5.リソグラフィー技術の進化と最先端の動向
- 5-1.光源の進化が微細化を牽引してきた歴史
- 5-2.次世代を担うEUV(極端紫外線)リソグラフィー技術
- 6.まとめ
- 7.用語まとめ
リソグラフィー技術は、電子機器に不可欠な半導体の製造を支える中心的な技術です。
写真の現像と似た原理を利用し、光を使ってシリコンウェーハ上に微細な電子回路のパターンを転写します。
この記事では、半導体の性能を決定づけるフォトリソグラフィの基本的な仕組みから、具体的な製造工程、そして最先端の技術動向までを網羅的に解説します。
リソグラフィー技術とは半導体製造に不可欠な微細加工技術
リソグラフィ技術とは、半導体チップの基板となるシリコンウェーハ上に、設計された回路パターンを正確に転写するための微細加工技術全般を指します。
その語源は石版画を意味する「リトグラフィ」にあり、版に描いた絵を転写する原理を応用したものです。
半導体製造においては、光を利用するフォトリソグラフィが主流であり、回路パターンが描かれた「フォトマスク」と呼ばれる原版を通して光を照射し、ウェーハ上に塗布された感光材にパターンを焼き付けます。
この技術によって、ナノメートル単位の極めて微細な電子回路を形成することが可能となり、半導体の高集積化と高性能化を実現する上で不可欠な役割を担っています。
写真の原理を応用したフォトリソグラフィの仕組み
フォトリソグラフィは、カメラで写真を撮影し現像するプロセスとよく似た仕組みを利用しています。
回路パターンが描かれた原版「フォトマスク」をネガフィルム、感光材である「フォトレジスト」を印画紙、そして光を照射する露光装置をカメラや引き伸ばし機に例えることができます。
この装置を使い、マスクを通過した光をレンズで縮小してウェーハ上に照射することで、設計通りの微細な回路パターンを正確に転写します。
半導体回路を形成するフォトリソグラフィの8つの主要工程
フォトリソグラフィによる回路パターンの形成は、単一の作業ではなく、複数の連続した工程を経て行われます。
基板となるウェーハの洗浄から始まり、感光材の塗布、露光、現像、そして不要な膜の除去まで、一連のプロセスは精密な管理下で進められます。
ここでは、フォトリソグラフィにおける代表的な主要工程を順に追いながら、ウェーハ上にどのようにして回路が刻まれていくのかを具体的に見ていきます。
①前処理:ウェーハ表面を洗浄し密着性を高める
フォトリソグラフィ工程の最初のステップは、ウェーハ表面を完全にクリーンな状態にする前処理です。
ウェーハ表面に微小なゴミや有機物、水分などが付着していると、次に塗布するフォトレジストが均一に塗れなかったり、うまく密着しなかったりして、回路パターンの欠陥に直結します。
そのため、薬品や純水を用いて徹底的に洗浄し、異物を除去します。
さらに、洗浄後は加熱して水分を完全に除去し、HMDSなどの薬品蒸気に晒すことでウェーハ表面を疎水性に変化させます。
これにより、フォトレジストとウェーハの密着性が向上し、後の現像やエッチング工程でのパターン剥がれを防ぎます。
②レジスト塗布:感光材(フォトレジスト)を均一に塗る
前処理を終えたウェーハ上に、感光性の液体化学物質であるフォトレジストを塗布します。
この工程で最も一般的に用いられるのが「スピンコート法」です。
まず、ウェーハの中心にフォトレジストを適量滴下し、その後、ウェーハを高速で回転させます。
このときに生じる遠心力によって、フォトレジストはウェーハ全面に広がり、均一な厚さの薄い膜を形成します。
回転速度や時間を精密に制御することで、ナノメートル単位で膜厚をコントロールすることが可能です。
ここで形成されるレジスト膜の厚さが均一でないと、後の露光工程で焦点がずれたり、エッチングの加工寸法にばらつきが生じたりするため、極めて高い精度が求められます。
③プリベーク:塗布したレジストを加熱し乾燥させる
レジスト塗布後、ウェーハは「プリベーク」または「ソフトベーク」と呼ばれる加熱工程に移ります。
これは、塗布されたばかりのフォトレジストに含まれている溶剤を蒸発させ、膜を乾燥させるために行います。
フォトレジストは液体であるため、溶剤が含まれていますが、これが残ったままだと、ウェーハとの密着性が低下したり、次の露光工程で感度が不安定になったりする原因となります。
ホットプレートなどを用いて、通常100℃前後の温度で数十秒から数分間加熱することで、溶剤を適切に除去し、レジスト膜を安定した状態にします。
この加熱温度や時間は、使用するフォトレジストの種類によって最適値が異なり、最終的なパターンの品質を左右する重要な管理項目の一つです。
④露光:マスクを通して回路パターンを光で焼き付ける
露光は、フォトリソグラフィ工程の中で最も重要なプロセスです。
ここでは、「ステッパー」や「スキャナー」と呼ばれる非常に高価で精密な露光装置が用いられます。
まず、石英ガラスなどで作られた原版「フォトマスク」に描かれた回路パターンを用意します。
そして、このマスクを通してウェーハ上のフォトレジストに光(紫外線など)を照射します。
すると、光が当たった部分のレジストだけが化学変化を起こします(ポジ型レジストの場合)。
レンズによってマスクのパターンは数分の一に縮小されてウェーハ上に投影されるため、元のマスクよりもはるかに微細な回路を形成できます。
この工程の解像度が、半導体チップの集積度、つまり性能を直接決定づけます。
⑤現像:不要になったレジストを薬品で溶かして除去する
露光工程が終わると、ウェーハは現像工程に移されます。
これは、露光によって化学的性質が変化したフォトレジストを選択的に除去し、回路パターンを可視化するプロセスです。
ウェーハを現像液と呼ばれるアルカリ性の薬品に浸したり、スプレーで吹き付けたりします。
一般的に使用されるポジ型レジストの場合、露光されて光化学反応を起こした部分が現像液に溶けやすくなっているため、その部分だけが除去されます。
逆にネガ型レジストでは、露光された部分が硬化し、光が当たらなかった部分が除去されます。
この結果、フォトマスクの回路パターンが転写されたレジストのパターンがウェーハ上に形成され、下層の膜を加工するための「マスク」として機能する準備が整います。
⑥ポストベーク:現像後のレジストパターンを硬化させ安定させる
現像によって形成されたレジストパターンをより強固なものにするため、「ポストベーク」または「ハードベーク」と呼ばれる加熱処理を行います。
この工程の主な目的は、現像後のレジストパターンを硬化させ、次のエッチング工程に対する耐性を向上させることです。
現像後のレジストには、まだ微量の溶剤や水分が残っている場合があり、これらを除去すると同時に、レジストの主成分である高分子を熱によって架橋・硬化させます。
これにより、レジストとウェーハ基板との密着性がさらに高まり、エッチングの際に使用される薬品やプラズマから下層の膜を保護するマスクとしての役割を確実に果たします。
この処理を怠ると、エッチング中にパターンが変形したり剥がれたりする恐れがあります。
⑦エッチング:レジストをマスクにして膜を削り回路を彫る
エッチングは、フォトリソグラフィで形成したレジストパターンをマスクとして利用し、ウェーハ上の薄膜を加工して実際に回路を形成する工程です。
レジストで覆われていない部分の薄膜を、化学薬品やガスを用いて選択的に除去します。
この加工方法には、ガスをプラズマ状態にしてイオンをぶつけることで物理的・化学的に削る「ドライエッチング」と、薬液に浸して化学反応で溶かす「ウェットエッチング」があります。
現代の微細な半導体製造では、加工精度が高く、垂直方向への加工が得意なドライエッチングが主流となっています。
このエッチング工程を経て、レジストパターンの形状が下地の薄膜に正確に転写され、電気的な機能を持つ回路構造が作り込まれます。
⑧レジスト剥離:役目を終えたレジストを取り除く
エッチングによって下層の膜に回路パターンが転写されると、マスクとして使われていたフォトレジストは不要になります。
そこで、この役目を終えたレジストをウェーハ上から完全に取り除くのがレジスト剥離の工程です。
剥離方法には、強力な有機溶剤などを含む専用の剥離液にウェーハを浸してレジストを溶解除去するウェット方式と、酸素プラズマを照射してレジストを灰化(アッシング)させて除去するドライ方式があります。
レジストがわずかでも残っていると、次の成膜工程などに影響を与えて欠陥の原因となるため、完全に除去することが極めて重要です。
この剥離工程が完了すると、ウェーハ上には目的の回路パターンのみが残り、フォトリソグラフィによる一つの層の形成が完了します。
なぜリソグラフィーは重要?半導体の性能を左右する微細化の鍵
半導体の性能は、一つのチップ上にどれだけ多くのトランジスタを搭載できるか(集積度)に大きく依存します。
リソグラフィー技術は、このトランジスタをつなぐ回路の線幅をより細くする「微細化」を実現する唯一の手段です。
回路を微細化できれば、同じ面積のチップにより多くの機能を詰め込めるだけでなく、信号の伝達速度が向上し、消費電力も削減できます。
しかし、微細化が進むほど、より精密なパターン形成が求められ、物理的な限界という課題に直面します。
そのため、リソグラフィー技術の進化が半導体全体の性能向上を直接左右する鍵となります。
リソグラフィー技術の進化と最先端の動向
半導体の集積度が指数関数的に向上するという「ムーアの法則」を支えてきたのは、リソグラフィー技術の絶え間ない進化でした。
より細かい回路パターンを描くため、技術者たちは露光に用いる光の波長を短くすることに注力してきました。
ここでは、g線からi線、そしてエキシマレーザーへと至る光源の進化の歴史を振り返るとともに、現在、最先端の半導体製造で導入されているEUV(極端紫外線)リソグラフィーという革新的な技術について解説します。
光源の進化が微細化を牽引してきた歴史
リソグラフィーによる微細化の歴史は、露光に用いる光源の短波長化の歴史とほぼ同義です。
初期の半導体製造では、水銀ランプの光(g線:波長436nm、i線:365nm)が使われていました。
その後、より微細な加工を目指して、波長の短いエキシマレーザーが開発され、KrFレーザー(248nm)、そしてArFレーザー(193nm)が主流となりました。
ArFレーザーの時代には、レンズとウェーハの間を純水で満たして屈折率を高める「液浸リソグラフィー」という技術が登場し、実質的により短い波長の光を使うのと同じ効果を得ることで、さらなる微細化を達成しました。
このように、光源をより波長の短いものへと置き換えていくことで、半導体産業は驚異的なスピードで性能向上を続けてきたのです。
次世代を担うEUV(極端紫外線)リソグラフィー技術
従来のArF液浸リソグラフィーが技術的限界に近づく中で、次世代の微細化を担う技術として登場したのがEUV(極端紫外線)リソグラフィーです。
EUVが用いる光は、波長が13.5nmとArFレーザーに比べて10分の1以下と極めて短く、これにより圧倒的に高い解像度を実現します。
しかし、この短い波長の光は空気やガラスレンズに吸収されてしまうため、従来の露光装置とは全く異なる構造が必要です。
装置内部は巨大な真空チャンバーとなり、光を透過させるレンズの代わりに、特殊な多層膜でコーティングされた反射ミラーを何枚も使って光を導きます。
開発には莫大なコストと時間がかかりましたが、現在では5ナノメートル以下の最先端ロジック半導体の量産に不可欠な技術となっています。
まとめ
リソグラフィー技術は、半導体チップ上に微細な回路パターンを形成するための中核的な製造技術です。
主流であるフォトリソグラフィは、写真の原理を応用し、感光材であるフォトレジストを塗布したウェーハに、フォトマスクを通して光を照射することでパターンを転写します。
このプロセスは、洗浄、塗布、露光、現像、エッチング、剥離といった複数の精密な工程で構成されます。
半導体の高性能化を支える微細化は、このリソグラフィー技術の解像度によって決まり、その進化は光源の短波長化、特に最先端のEUV技術によって牽引されています。
用語まとめ
リソグラフィー(Lithography)
半導体製造で、光を使って回路パターンをシリコンウェーハ上に転写する微細加工技術。語源はギリシャ語で「石に書く」を意味する lithos + graphein。
フォトリソグラフィ(Photolithography)
光を利用して感光材に回路パターンを焼き付ける方式。現在の半導体製造の中心技術で、ナノメートル単位の精度で回路を描く。
シリコンウェーハ(Silicon Wafer)
半導体チップの基板となる薄いシリコン円盤。上に何層もの回路を形成していく。
フォトマスク(Photomask)
設計した電子回路の原版。石英ガラスなどにパターンを描き、露光工程で光を通す“版”の役割を果たす。
フォトレジスト(Photoresist)
光に反応する感光性樹脂。露光によって化学反応し、現像工程でパターンを形成する。
スピンコート法(Spin Coating)
ウェーハを高速回転させ、フォトレジストを均一な薄膜として塗布する方法。膜厚の均一性が極めて重要。
プリベーク(Prebake / Soft Bake)
レジスト塗布後に加熱し、溶剤を蒸発させて膜を安定化させる工程。次の露光精度を左右する。
露光(Exposure)
フォトマスクを通して光を照射し、レジストにパターンを焼き付ける工程。リソグラフィーの最重要ステップ。
ステッパー/スキャナー(Stepper / Scanner)
マスクのパターンをレンズで縮小投影する高精度露光装置。現在はスキャン方式が主流。
現像(Development)
露光後、薬液で不要なレジストを溶かしてパターンを浮かび上がらせる工程。ポジ型・ネガ型で反応が逆になる。
ポジ型レジスト(Positive Resist)
光を当てた部分が現像液で溶けるタイプ。微細加工に適しており、現在の主流。
ネガ型レジスト(Negative Resist)
光を当てた部分が硬化し、光の当たらなかった部分が溶けるタイプ。耐久性が高いが、解像度はやや低い。
ポストベーク(Postbake / Hard Bake)
現像後のレジストを加熱して硬化・安定化させる工程。エッチング時の剥離を防ぐ。
エッチング(Etching)
レジストをマスクにして、下層の膜を削る工程。ドライ(プラズマ)方式が主流で、ナノ精度の加工が可能。
ドライエッチング(Dry Etching)
ガスをプラズマ化してイオン衝撃で削る加工法。垂直方向に精密なパターンを形成できる。
ウェットエッチング(Wet Etching)
薬液で化学的に材料を溶かす加工法。コストが低いが、加工方向の制御が難しい。
アッシング(Ashing)
酸素プラズマでレジストを灰化・除去する工程。剥離の一種で、環境負荷が少ない。
微細化(Miniaturization)
トランジスタや配線の線幅を縮小すること。集積度・性能・省電力性の向上に直結する。
ムーアの法則(Moore’s Law)
「半導体の集積度は約18〜24か月ごとに倍増する」という経験則。リソグラフィーの進化が支える。
g線・i線(g-line / i-line)
水銀ランプの光源の一種。g線は波長436nm、i線は365nmで、初期の半導体露光に使用された。
エキシマレーザー(Excimer Laser)
短波長の紫外光を発生させるレーザー。KrF(248nm)やArF(193nm)が主流となり、微細化を加速。
液浸リソグラフィー(Immersion Lithography)
レンズとウェーハの間に純水を満たすことで屈折率を上げ、実質的に短波長化を実現した技術。
EUVリソグラフィー(Extreme Ultraviolet Lithography)
波長13.5nmの極端紫外線を利用した最先端技術。真空環境と反射ミラー光学系を使用し、5nm以下の回路形成を可能にする。
多層膜ミラー(Multilayer Mirror)
EUV光を反射させるための特殊コーティングミラー。ガラスでは透過できない短波長光を制御する。
真空チャンバー(Vacuum Chamber)
EUV露光装置内部の真空空間。EUV光は空気に吸収されるため、露光工程全体を真空下で行う。
ナノメートル(nm)
1nm=10⁻⁹メートル。リソグラフィーでは線幅の単位として使われ、半導体の世代を示す基準となる。

西進商事コラム編集部
西進商事コラム編集部です。専門商社かつメーカーとしての長い歴史を持ち、精密装置やレーザー加工の最前線を発信。分析標準物質の活用も含め、さまざまなコラム発信をします。
