
- INDEX目次
目次【非表示】
- 1.リニアモータとは?仕組み・原理・構造から工作機械での利点まで解説
- 2.リニアモータの基礎知識|回転しないモータとは?
- 2-1.回転モータとの違い
- 3.リニアモータが動く仕組みと基本的な構造
- 3-1.磁石の力で直線運動を生み出す動作原理
- 3-2.回転モータを直線状に展開したシンプルな構造
- 4.リニアモータの強み(メリット)
- 4-1.高速かつ精密な位置決めが可能
- 4-2.機械的な接触がなく静音性に優れる
- 4-3.シンプルな構造でメンテナンスが容易
- 5.リニアモータの弱み(デメリット)
- 5-1.強力な磁力による安全対策が必要になる
- 5-2.発熱しやすく冷却装置が求められる場合がある
- 6.【種類別】リニアモータの主な特徴
- 6-1.高精度な制御が得意なリニア同期モータ
- 6-2.構造がシンプルで扱いやすいリニア誘導モータ
- 6-3.小型化に適したリニア直流モータ
- 6-4.特定の周波数で動作するリニア共振アクチュエータ
- 7.リニアモータの選び方のポイント
- 8.リニアモータはどんな工作機械で使われている?
- 8-1.高精度な加工が求められるマシニングセンタ
- 8-2.高速動作が必要な切削加工機や研削盤
- 8-3.微細な加工を実現する放電加工機
- 9.まとめ
リニアモータとは?仕組み・原理・構造から工作機械での利点まで解説
リニアモータとは、回転運動を直線運動に変換する機構を介さず、直接的な直線運動を生み出すモータのことです。この記事では、そんなリニアモータとは何か、その仕組みや原理、構造といった基礎知識から、メリット・デメリット、さらには工作機械などの具体的な用途までを網羅的に解説します。
リニアモータの基礎知識|回転しないモータとは?
リニアモータは、一般的なモータが回転運動を生み出すのに対し、電力から直接的に直線運動を得る装置です。
直線運動を行う※アクチュエータの一種であり、ボールねじや歯車といった回転運動を直線運動に変換する機械的な部品が不要なため、高速かつ精密な動作を実現します。
この特性から、様々な産業分野で活用が進んでいます。
アクチュエーターとは、電気や空気などのエネルギーを使って“動き”を生み出す装置のこと。
具体的には以下のようなものを指します。
モーター:電気を使って回転させる(ロボットの腕を動かす、ファンを回す)
油圧シリンダー:油の圧力で押し出したり引っ込めたりする(建設機械のアームなど)
空気圧シリンダー:圧縮空気で動く(工場の自動ラインでモノを押す)
ピエゾアクチュエータ:電圧で超微細に動く(カメラの手ぶれ補正など)
回転モータとの違い
回転モータは、円筒状の固定子と回転子が電磁石の働きで磁気吸引・反発を繰り返し、回転運動を生み出す装置です。例えば、扇風機や洗濯機、自動車のエンジンなど、身の回りの多くの機器に利用されています。一方、リニアモータは、回転モータの固定子と回転子を直線状に展開したような構造を持ち、直線運動を直接生み出す点が大きく異なります。一般的な回転モータの場合、回転運動を直線運動に変換するために、ボールねじやラックアンドピニオンといった機械的な要素が必要になりますが、リニアモータではこれらの変換機構が不要です。この構造の違いが、リニアモータならではのメリットを多数生み出しています。具体的には、機械的な接触部分が少ないため、部品の摩耗が少なくなり、静音性やメンテナンス性の向上に貢献しているのです。また、摩擦やバックラッシュ(機械的な遊び)の影響を受けないため、より高速かつ精密な位置決めが可能となります。このように、リニアモータは、回転モータでは実現が難しい、高精度でダイレクトな直線駆動を可能にする、革新的なモータと言えるでしょう。
リニアモータが動く仕組みと基本的な構造
リニアモータが動く仕組みは、磁石とコイルの間に働く電磁気的な力を利用しています。
この仕組みの基本は、回転モータを直線状に切り開いたものと考えると理解しやすいでしょう。
固定子と可動子から成るシンプルな構造を持ち、機械的な接触部品が少ないため、直接的な駆動力で効率よく直線運動を生み出します。

磁石の力で直線運動を生み出す動作原理
リニアモータの動作の原理は、フレミングの左手の法則に基づいています。
一般的に、永久磁石が配置された固定子(ステータ)と、コイルが巻かれた可動子(ムーバ)で構成されます。
可動子のコイルに電流を流すと磁界が発生し、固定子の磁石との間にローレンツ力(吸引力や反発力)が生じます。
この電磁気的な力を推進力として、可動子が直線方向に動きます。
電流の向きや強さを制御することで、可動子の位置や速度、加速度を精密にコントロールすることが可能です。
回転モータを直線状に展開したシンプルな構造
リニアモータの基本的な構造は、回転モータの固定子と回転子を一直線上に切り開いて配置した形と捉えることができます。
固定子側には永久磁石、可動子側にはコイルが配置されるのが一般的です。
このシンプルな設計により、ボールねじやギアなどの機械的な伝達機構が不要となり、部品点数の削減や装置全体の小型化に貢献します。
また、コイル部分に鉄心を持つコア付き方式と、持たないコアレス方式が存在し、用途に応じて推力や速度特性の異なる方式が選択されます。
リニアモータの強み(メリット)
リニアモータは、独自の構造から多くのメリットをもたらします。
機械的な伝達機構を必要としないため、高速かつ高精度な位置決めが可能になる点が最大の強みです。
また、非接触駆動による静音性の高さや、摩耗部品が少ないことによるメンテナンス性の良さも大きな利点であり、生産性の向上や装置の長寿命化に貢献します。
高速かつ精密な位置決めが可能
リニアモータは、ボールねじやギアといった機械的な伝達機構を介さずに直接駆動するため、高速な動作を実現します。
機械部品に起因する応答遅れや慣性の影響を受けにくく、優れた加減速性能を発揮できます。
また、バックラッシや摩耗が存在しないため、長期間にわたって高い位置決め精度を維持することが可能です。
これにより、ナノメートル単位の精密な位置決めが求められる半導体製造装置や、高速なタクトタイムが必要な搬送装置など、高い速度と精度が両立されるべき用途で強みを発揮します。
機械的な接触がなく静音性に優れる
リニアモータは、固定子と可動子が非接触の状態で駆動するため、動作時の騒音や振動が極めて少ないという特徴があります。
ボールねじやギア駆動で発生しがちな機械的な摩擦音や摺動ノイズがなく、非常に静かな動作環境を実現します。
この静音性は、医療機器や精密測定器など、静粛性が求められる装置において大きな利点です。
また、振動が少ないことは、加工精度や検査精度に影響を与えにくいため、高品質なものづくりにも貢献します。
さらに、摩耗による発塵も少ないため、クリーンルーム内での使用にも適しています。
シンプルな構造でメンテナンスが容易
リニアモータは、回転モータとボールねじなどを組み合わせた機構に比べて構造がシンプルで、部品点数が少ないのが特徴です。
駆動部に機械的な接触部品がほとんどないため、摩耗や経年劣化が少なく、定期的な潤滑剤の塗布や部品交換といったメンテナンスの頻度を大幅に削減できます。
これにより、装置のダウンタイムが短縮され、生産性の向上に寄与します。
高い出力を維持しつつも、長期的に安定した稼働が期待できるため、ランニングコストの低減にもつながります。
このメンテナンス性の高さは、24時間稼働するような生産ラインにおいて特に重要な要素です。
リニアモータの弱み(デメリット)
多くの利点を持つリニアモータですが、導入を検討する際にはいくつかの欠点も理解しておく必要があります。
特に、強力な永久磁石を使用することに起因する安全上の配慮や、高出力時に発生する熱への対策が課題となる場合があります。
これらのデメリットを事前に把握し、適切な対策を講じることが、リニアモータを効果的に活用する鍵となります。
強力な磁力による安全対策が必要になる
リニアモータ、特に高推力を生み出すタイプでは、非常に強力な永久磁石が使用されます。
この強力な磁力は、周辺の金属物を引き寄せる危険があるため、設置やメンテナンス時には工具の取り扱いに細心の注意を払わなければなりません。
また、クレジットカードなどの磁気カードや、時計、精密電子機器などに影響を与えてデータを破損させたり、故障させたりする可能性があります。
さらに、心臓ペースメーカーなどの医療機器を装着している作業者は、磁場の影響を避けるために立ち入りが制限されるなど、作業環境における厳格な安全対策と管理体制の構築が不可欠です。
発熱しやすく冷却装置が求められる場合がある
リニアモータは、コイルに電流を流して推力を得る仕組み上、ジュール熱による発熱が避けられません。
特に、高速・高頻度で加減速を繰り返すような運転では、コイル部分の温度が著しく上昇します。
この発熱は、モータ自体の性能低下を招くだけでなく、熱膨張によって周辺の機械部品を変形させ、加工精度や位置決め精度に悪影響を及ぼす可能性があります。
そのため、高性能なリニアモータを安定して使用するには、水冷ジャケットや空冷ファンといった冷却装置を併設し、適切に熱を管理することが重要になります。
この冷却システムの追加は、コストや設置スペースの増加につながる要因です。
【種類別】リニアモータの主な特徴
リニアモータには、駆動原理や構造によっていくつかの種類が存在し、それぞれに異なる特徴があります。
代表的なものとして、リニア同期モータ、リニア誘導モータ、リニア直流モータが挙げられます。
この他にも、パルス信号で駆動するリニアステッピングモータや、円筒形状を持つタイプなど、用途に合わせて多様な製品が開発されています。
小型・薄型化されたモデルもあり、装置の設計自由度を高めています。

高精度な制御が得意なリニア同期モータ
リニア同期モータは、可動子に永久磁石、固定子に3相コイル(またはその逆)を配置し、電流の周波数と可動子の移動速度が完全に同期するモータです。
ACサーボモータを直線化したものと考えることができ、サーボドライバとエンコーダを組み合わせることで、極めて高精度な位置・速度・推力の制御を実現します。
この優れた制御性から、サブミクロン単位の位置決め精度が要求される工作機械、半導体露光装置、精密測定器などで広く採用されています。
構造によってコア付き、コアレスのタイプがあり、用途に応じて最適なものが選択されます。
構造がシンプルで扱いやすいリニア誘導モータ
リニア誘導モータは、固定子側のコイルに交流電流を流して移動磁界を発生させ、電磁誘導の原理によって可動子側の導体に誘導電流を発生させて推力を得る方式です。
このリニア誘導モーターは、可動子に永久磁石を使用せず、単純な導体板(アルミや銅)で構成できるため、構造がシンプルで堅牢、かつ比較的安価に製造できるという利点があります。
精密な同期制御は難しいものの、大きな推力を得やすく、リニアモーターカーや工場の搬送ライン、シャッターの開閉装置など、高速・高推力が求められる用途で利用されています。
小型化に適したリニア直流モータ
リニア直流モータは、その名の通り直流(DC)電源で駆動するリニアモータです。
ブラシ付きとブラシレスのタイプがあり、特にブラシレスDCリニアモータは、ホール素子などを用いて磁極位置を検出し、電流を切り替えることで直線運動を生み出します。
駆動回路が比較的シンプルで、モータ自体の小型・軽量化が容易なため、スペースに制約のある装置や小型の精密機器への組み込みに適しています。
大きな推力を出すのは得意ではありませんが、応答性が高く、マイクロメートル単位での微小なストロークや精密な位置決めが求められる光学機器のピント調整や、医療機器のサンプルステージ駆動などに活用されています。
特定の周波数で動作するリニア共振アクチュエータ
リニア共振アクチュエータは、特定の周波数で共振現象を利用し、効率的な直線運動を発生させる特殊なリニアモータです。このタイプのアクチュエータは、機械的な接触なしで振動するため、静音性に優れており、高い耐久性を持ちます。主に、微細な動きや精密な振動を必要とする用途で真価を発揮し、たとえば携帯電話の触覚フィードバック(バイブレーション機能)や、医療機器、精密検査装置などに広く採用されています。共振周波数に合わせて設計されるため、他のリニアモータと比較して駆動効率が高く、小型化しやすいという特長もあります。しかし、動作が特定の周波数に限定されるため、幅広い速度や位置での制御が求められる用途には不向きな場合があります。そのため、その特性を理解し、用途に応じて適切に選択することが重要です。
リニアモータの選び方のポイント
リニアモータを選定する際は、使用するシステムの要求性能と環境条件を詳細に考慮することが重要です。まず、リニアモータが駆動させる必要のある負荷の容量を確認し、適切な出力とサイズを選定します。次に、必要とされる最大速度と加速度を明確に設定してください。特に、高速移動や急加速・急減速が求められる用途では、この点が非常に重要になります。また、精密な位置制御が不可欠なアプリケーションでは、リニアモータの分解能や繰り返し位置決め精度が選定基準となります。これには、エンコーダの選定も含まれるため、システム全体の精度要件に合わせて慎重に検討する必要があります。
さらに、リニアモータが使用される環境条件も考慮しなければなりません。高温多湿や粉塵が多い環境など、厳しい条件下で使用する場合は、それに耐えうる特性を持つモータを選ぶ必要があります。例えば、発熱しやすいリニアモータの場合、冷却装置の有無や冷却方法も重要な検討項目です。
リニアモータには「コア付型」と「コアレス型」の主な2種類があり、それぞれの特性を理解して選ぶことが大切です。コア付型は、コイルが鉄心に巻かれているため高い推力を発揮しますが、磁石と鉄心間の吸引力によるコギング(動作の滑らかさを阻害する磁気的な抵抗)が発生しやすく、速度安定性が劣る場合があります。一方、コアレス型は鉄心がないためコギングがなく、非常に滑らかで安定した動作が可能です。ただし、コア付型に比べて一般的に推力が低めであるため、用途に応じた選択が求められます。
サプライヤーを選定する際には、カスタム対応が可能かどうかも重要なポイントです。小型化や大出力化、あるいは特定の速度・位置決め精度など、独自のニーズがある場合は、特注に対応できるメーカーを選ぶことで、最適なリニアモータシステムを構築できるでしょう。
リニアモータはどんな工作機械で使われている?
リニアモータの優れた特性は、様々な産業分野で活かされており、特に高い精度と生産性が求められる工作機械の分野でその用途が広がっています。
従来のボールねじ駆動では達成が難しかった高速・高精度な加工を実現するため、多くの最新鋭の工作機械でリニアモータ駆動が採用されています。
ここでは、その代表的な例をいくつか紹介します。
高精度な加工が求められるマシニングセンタ
マシニングセンタでは、ワークを載せるテーブルのX軸、Y軸、Z軸の駆動にリニアモータが採用されています。
従来のボールねじ駆動に比べてバックラッシがなく、機械的な遅れや振動が少ないため、指令に対して極めて忠実なテーブル移動が可能です。
これにより、金型の複雑な自由曲面加工や、精密部品の輪郭加工において、非常に滑らかで高品位な加工面を実現します。
また、優れた加減速性能を活かしてテーブルの高速送りを実現し、非切削時間を短縮することで、全体のサイクルタイムを短縮し、生産性の向上に大きく貢献しています。
高速動作が必要な切削加工機や研削盤
切削加工機や研削盤においても、リニアモータの高速性が生産性向上に直結します。
工具やワークテーブルの高速な往復運動や位置決めが可能になるため、加工時間を大幅に短縮できます。
特に小物部品の大量生産ラインなどでその効果を発揮します。
この高速・高応答という特性は、工作機械以外の分野でも広く活用されています。
例えば、半導体製造装置におけるウェハの高速搬送ステージや、液晶パネルの製造ライン、電子部品を実装するチップマウンター、製品を仕分ける高速ピックアンドプレースロボットなど、タクトタイムの短縮が求められる様々な自動化設備で重要な役割を担っています。
微細な加工を実現する放電加工機
放電加工機は、電極とワークの間に微細なギャップを保ちながら放電を繰り返すことで加工を行うため、極めて精密な位置制御が求められます。
ここでリニアモーター駆動が大きな利点をもたらします。
リニアモータは応答性が非常に高く、加工中のギャップ変動に対して素早く追従できるため、安定した放電状態を維持し、加工精度と速度を向上させます。
摩耗による精度劣化がないため、長期間にわたって高精度な加工が可能です。
多くの場合、直線運動を案内するリニアガイドと一体化したリニアモータガイドとしてシステムに組み込まれ、滑らかで精密な電極の送りを実現しています。
まとめ
リニアモータ技術は、日本の首都圏を走る地下鉄、例えば都営大江戸線のような鉄道車両の駆動方式にも採用されています。
車輪とレールの摩擦に頼らないため、急勾配に強いという利点があります。
また、一部のエレベータでもリニアモーター駆動が利用され、静かで滑らかな乗り心地を提供しています。
国によっては、リニアモーターカーが次世代の高速鉄道として期待されています。
こうした大規模な交通インフラだけでなく、発電や超音波を利用した特殊なモータなど、応用範囲は多岐にわたります。
nskをはじめ国内外の多くのメーカやメーカーが開発を進めており、その技術情報は英語や中文などでも発信されています。
駅のホームドアや遊園地の乗り物など、意外な場所でもこの技術は活躍しています。

西進商事コラム編集部
西進商事コラム編集部です。専門商社かつメーカーとしての長い歴史を持ち、精密装置やレーザー加工の最前線を発信。分析標準物質の活用も含め、さまざまなコラム発信をします。

PLCとは?シーケンサとは?わかりやすくどんな装置か基礎知識を徹底解説!
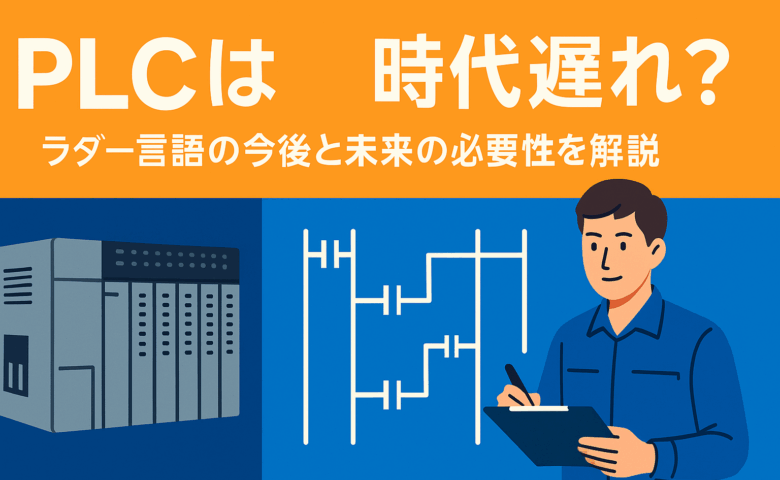
PLCは時代遅れ?ラダー言語の今後と未来の必要性を解説
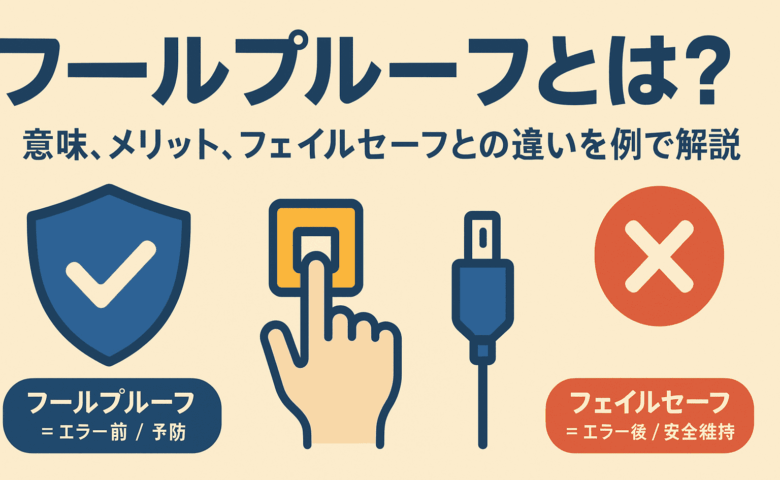
フールプルーフとは?意味、メリット、フェイルセーフとの違いを例で解説

スチームトラップとは?知らないと損する種類や仕組みについて解説

