
グリーン半導体は、省エネルギー性能を大幅に向上させた次世代半導体の総称です。現在、日本政府が掲げる2050年カーボンニュートラル目標の達成に向けて、経済産業省が国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)に造成した「グリーンイノベーション基金」が、「次世代デジタルインフラの構築」プロジェクトを推進しています。このプロジェクトは、グリーンイノベーションの一環として、次世代パワー半導体や次世代グリーンデータセンターの開発を支援し、半導体分野における温室効果ガス排出削減に貢献することを目指しています。<br>
本記事ではグリーン半導体について解説するとともに、記事最後では関連する用語もまとめて説明します。
はじめに:グリーン半導体とは何か?
グリーン半導体とは、半導体の製造から廃棄に至るまでのライフサイクル全体で、CO2排出量などの環境負荷を低減する技術を指します。あらゆる産業の基盤を支える半導体は、現代社会にとって不可欠な存在ですが、その製造には大量の資源とエネルギーが消費され、環境への影響が課題となっています。そこで、持続可能な社会の実現に向けて、環境負荷の低い製造プロセスや素材の開発、省エネルギー性能の高いグリーンパワー半導体などの製品開発が進められています。これは、半導体製造を持続可能(サステナブル)にするための重要な取り組みであり、2020年頃から世界の半導体産業全体で推進されています。
なぜ今、半導体分野でグリーン化が必要とされているのか

デジタル技術の急速な発展に伴い、半導体はあらゆる産業において不可欠な存在となりました。半導体の製造には、クリーンルームの維持や特殊ガスの使用、大量の電力消費など、多くのエネルギーと資源が必要です。このため、半導体製造は環境負荷が大きい産業の一つとされており、持続可能な社会を実現するためには、半導体分野におけるグリーン化の推進が喫緊の課題となっています。
特に、AIやIoT、自動運転などの技術が普及するにつれて、半導体の需要は今後も増加し続けると予測されています。しかし、このままでは地球温暖化の原因となる温室効果ガスの排出量も増大する一方です。そこで、製造プロセスの効率化や再生可能エネルギーの導入、そして低消費電力のグリーン半導体への転換が求められています。これにより、半導体のライフサイクル全体で環境負荷を低減し、カーボンニュートラル社会の実現に貢献できると期待されています。
グリーンイノベーション基金が主導する「グリーン半導体S」プロジェクト
「グリーン半導体S」プロジェクトは、2050年のカーボンニュートラル実現を目指すグリーンイノベーション基金事業の一環として、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)が推進しています。このプロジェクトは、半導体分野における省エネルギー化と環境負荷低減を目的としており、次世代パワー半導体やデータセンターの省エネ化、エッジコンピューティング技術の開発などを主な研究開発項目としています。特に、産業技術総合研究所(産総研)が設立した「グリーンサステナブル半導体製造技術検討会」とも連携し、半導体製造プロセス全体のグリーン化に向けた共通指標の策定も進められています。
【研究開発①】省エネルギー化の鍵を握る次世代パワー半導体の製造技術
グリーンイノベーション基金事業では、省エネルギー化を実現する「次世代グリーンパワー半導体」の開発が特に重要視されています。パワー半導体は、電気自動車や産業機器、データセンターなど、幅広い電気機器の電力変換や制御に不可欠なデバイスです。従来のシリコン(Si)製パワー半導体には電力損失が大きいという課題があり、これに代わるSiC(炭化ケイ素)やGaN(窒化ガリウム)といった新素材を用いた次世代パワー半導体の製造技術開発が進められています。
SiCとGaNは、Siに比べて高耐電圧・低損失という優れた特性を持ち、電力効率を大幅に向上させる可能性を秘めています。例えば、SiCパワー半導体は高耐圧が必要な電力系統や鉄道分野での活用が期待されており、GaNパワー半導体は高周波での高速スイッチングが可能なため、ACアダプターやサーバー電源などの小型化・高効率化に適しています。
グリーンイノベーション基金は、2030年までに次世代パワー半導体を用いた電力変換器の損失を50%以上低減し、かつ従来のSiパワー半導体と同等のコストで量産することを目指しています。具体的には、8インチSiC MOSFETや高耐圧SiCモジュールの開発、さらに高電力密度産業用電源向けのGaNパワーデバイスの開発などが重点的に進められています。これらの技術開発は、日本の産業競争力強化とカーボンニュートラル社会の実現に大きく貢献すると期待されています。
【研究開発②】性能向上に不可欠な次世代ウェハ技術の開発
グリーン半導体の性能向上には、基盤となるウェハ技術の進化が不可欠です。特に、シリコン(Si)に代わる炭化ケイ素(SiC)や窒化ガリウム(GaN)といった新素材を用いた次世代ウェハの開発が注目されています。これらの新素材は、従来のSiよりも高耐電圧、低損失、高速スイッチングなどの優れた特性を持ち、電気自動車(EV)や再生可能エネルギー、データセンターなど、幅広い分野での省エネルギー化に貢献します。
次世代ウェハ技術では、SiCウェハの大口径化と高品質化が重要な課題です。現在主流の6インチから8インチへの大口径化により、一度に製造できる半導体チップの数が増え、製造コストの削減と生産効率の向上が期待されます。また、結晶欠陥の低減も不可欠で、これにより半導体デバイスの信頼性が向上します。グリーンイノベーション基金事業では、溶液法やプロセス・インフォマティクス技術を活用したSiC結晶成長技術の開発、および大口径SiCウェハ向けの加工・評価技術の開発が進められています。
また、半導体の微細化技術も性能向上とエネルギー効率の改善に大きく寄与します。トランジスタの小型化によって、単位面積あたりの集積度が高まり、処理速度の向上と消費電力の削減が実現します。この技術は、スマートフォンやデータセンター、AI、自動運転車など、多様な応用分野で重要な役割を担っており、グリーン半導体Sプロジェクトにおいても、こうした最先端のウェハ技術開発がグリーンデジタル社会の実現を後押ししています。
【研究開発③】データセンターの消費電力を大幅に削減する新技術
データセンターは、デジタル社会を支える基盤として、DX(デジタルトランスフォーメーション)とGX(グリーントランスフォーメーション)を推進する上で不可欠な存在です。しかし、データ量の爆発的な増加に伴い、データセンターの消費電力も急増しており、そのグリーン化が喫緊の課題となっています。実際に、世界のデータセンターの総年間消費電力は、ほぼ4年ごとに倍増しているというデータもあります。2030年には、世界の発電量の10分の1をデータセンターが消費するとの試算もあり、これまでの技術進化による消費電力削減だけでは、増加する電力消費量に追いつかないと予想されています。
この課題に対し、NEDOのグリーンイノベーション基金プロジェクトでは、次世代グリーンデータセンター技術の開発を推進しており、2021年度に普及していたデータセンターと比較して、40%以上の省エネ化を目指しています。具体的には、サーバー内の電気配線を光配線化する「光電融合技術」や、サーバー全体を液体に浸して冷却する「液浸冷却システム」などが注目されています。
光電融合技術は、チップ間の接続における消費電力を90%削減し、データセンターネットワーク全体の消費電力を25%削減する可能性を秘めています。また、液浸冷却システムは、空気よりも熱伝導率の高い液体を活用することで、冷却ファンが不要となり、データセンターのPUE(電力使用効率)を1.05から1.07程度にまで大幅に改善できると期待されています。実際に、KDDIなどは、サーバーを潤滑油に浸して冷却する「液浸」システムを開発し、空調冷却と比較して冷却に必要な電力を94%削減できることを確認しています。
これらの革新的な冷却技術や省電力化技術によって、データセンターの消費電力を大幅に削減し、持続可能なデジタル社会の実現に貢献できると期待されています。
グリーン半導体によって実現する持続可能なデジタル社会
グリーン半導体は、持続可能なデジタル社会を実現するための基盤技術として、大きな期待が寄せられています。デジタル化の進展に伴い、半導体の需要は高まる一方で、その製造には大量の資源とエネルギーが消費され、環境負荷が懸念されています。グリーン半導体は、製造プロセス全体におけるCO2排出量の削減や資源の有効活用を目指すもので、この課題解決に不可欠です。
特に、グリーンイノベーション基金が推進する研究開発プロジェクトは、次世代パワー半導体や次世代ウェハ技術、データセンターの省電力化など、多岐にわたる分野でグリーン半導体の実現を後押ししています。例えば、パワー半導体の省エネルギー化は、電気自動車や再生可能エネルギー系統、家電製品など、幅広い分野での消費電力削減に貢献し、脱炭素社会の実現に寄与します。
また、データセンターにおける電力消費量の削減も、グリーン半導体によって大きく進展します。AI半導体の電力消費量は近年急増しており、データ流通量の増加に伴い、データセンターの消費電力は今後さらに拡大すると予測されているため、グリーン半導体による省電力化は、デジタル社会の持続性を確保する上で非常に重要です。
グリーン半導体の開発と普及は、デジタル経済の成長と環境保護の両立を可能にするグリーンイノベーションの中核をなします。これにより、資源枯渇や気候変動といった地球規模の課題に対処しつつ、より豊かで持続可能なデジタル社会の実現を目指すことができるのです。
まとめ
グリーン半導体は、現代社会のデジタル化を支える重要なインフラであり、持続可能な社会を実現するために不可欠な技術です。半導体製造プロセスにおける環境負荷の低減は喫緊の課題であり、サプライチェーン全体でのCO2排出削減や資源消費の抑制が求められています。
グリーンイノベーション基金事業では、「次世代グリーンパワー半導体」の開発を推進し、電動車や再生可能エネルギーなどの分野で革新的な省エネルギー化を目指しています。具体的には、従来のシリコンに代わるSiCやGaNといった新素材を用いた次世代パワー半導体の製造技術やウェハ技術、データセンターの消費電力を大幅に削減する技術開発が進められています。これらの取り組みにより、高性能化と環境負荷低減の両立が期待され、脱炭素社会の実現に大きく貢献するでしょう。
用語解説
カーボンニュートラル
温室効果ガスの排出量と吸収量を差し引きゼロにする考え方。2050年に世界的な達成を目指している。
NEDO(新エネルギー・産業技術総合開発機構)
日本の国立研究開発法人。エネルギー、環境、産業技術に関する研究開発を推進する組織。
グリーンイノベーション基金
日本政府が設けた2兆円規模の基金。脱炭素社会の実現に向けた研究開発や実証を長期的に支援する。
パワー半導体
電気を「変換・制御」するための半導体。電気自動車や産業機器、データセンターなどで使われ、省エネ性能に直結する。
SiC(炭化ケイ素)
シリコンの代替材料。高耐圧・低損失に優れ、鉄道や送電システムなど高電力用途に使われる。
GaN(窒化ガリウム)
高速スイッチングが得意な半導体材料。小型の充電器やサーバー電源など高周波・高効率が必要な分野に適する。
MOSFET(Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor)
電力を効率的に制御するトランジスタの一種。パワー半導体の代表的デバイス。
ウェハ(Wafer)
半導体チップを作るための基板。シリコンやSiC、GaNなどの材料を薄い円盤状に加工したもの。
大口径化
ウェハの直径を大きくすること。一度に作れるチップ数が増え、コスト低減につながる。
プロセス・インフォマティクス
AIやデータ解析を使って製造プロセスを最適化する技術。歩留まり改善や不良削減に活用される。
光電融合技術
電気配線の代わりに光(フォトニクス)を用いてチップやサーバー間を接続する技術。消費電力を大幅に削減できる。
液浸冷却システム
サーバーを液体に浸して冷やす方式。空調冷却より効率的で、省エネ効果が高い。
PUE(Power Usage Effectiveness)
データセンターの省エネ指標。数値が1に近いほど効率的。
DX(デジタルトランスフォーメーション)
デジタル技術でビジネスや社会の仕組みを変革すること。
GX(グリーントランスフォーメーション)
脱炭素や省エネを前提にした社会・経済システムの変革。

西進商事コラム編集部
西進商事コラム編集部です。専門商社かつメーカーとしての長い歴史を持ち、精密装置やレーザー加工の最前線を発信。分析標準物質の活用も含め、さまざまなコラム発信をします。
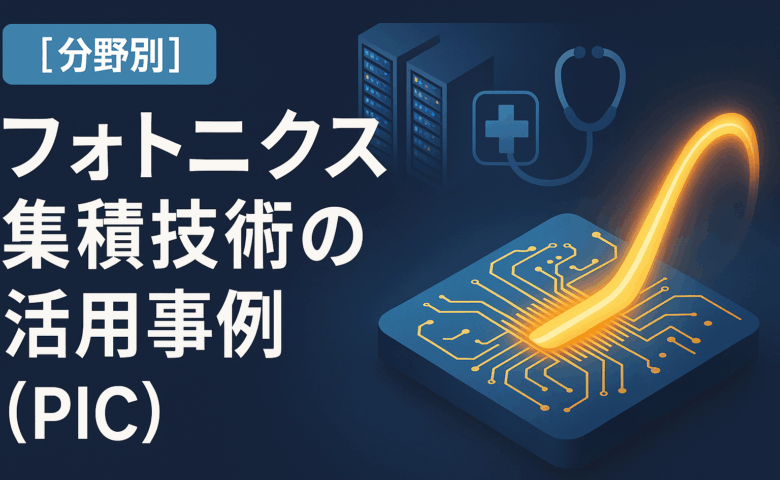
フォトニクス集積とは?高速伝送・省電力を実現する技術を解説

