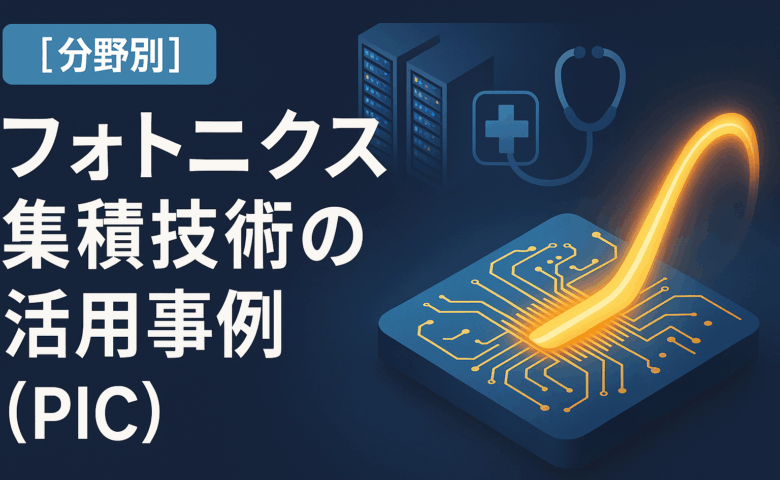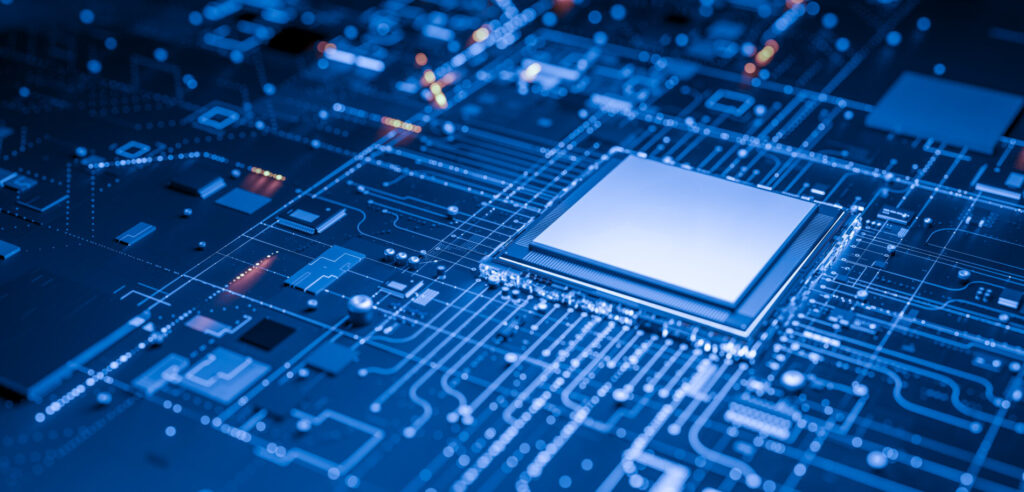
- INDEX目次
目次【非表示】
- 1.2nmプロセスとは?次世代半導体の性能を飛躍させる革新的技術
- 2.なぜ半導体の微細化は重要?性能向上と省電力化の歴史
- 3.「2nm」は実際の長さではない?プロセスルールの数字が示す意味
- 4.2nmプロセスの鍵を握る新技術「GAAトランジスタ」の仕組み
- 4-1.電流の制御能力を向上させるGAA構造とは
- 5.従来のFinFET構造との決定的な違い
- 6.2nmプロセスの製造が極めて困難とされる3つの理由
- 6-1.ナノシートの精密な加工に求められる超高精度技術
- 6-2.リーク電流を防ぐための新材料導入と課題
- 6-3.量産化の鍵となる最先端の露光技術
- 7.世界の主要メーカーによる2nmプロセス開発競争の最前線
- 8.2nmプロセスの実用化で私たちの生活はどう変わる?
- 9.まとめ
- 10.用語解説
2nmプロセスとは、半導体チップの回路線幅を2ナノメートル級まで微細化した、次世代の製造プロセス技術です。これは、1ナノメートルが10億分の1メートルという極めて微細な世界で、スマートフォンやAI用アクセラレータなどの高性能な半導体に不可欠とされています。ただし、「2nm」という数字は、トランジスタの物理的なゲート長を直接示すものではなく、技術世代の名称として使用されている点に注意が必要です。
2nmプロセスとは?次世代半導体の性能を飛躍させる革新的技術
2nmプロセスとは、半導体チップの回路線幅を2ナノメートル級まで微細化する次世代プロセス技術を指します。1ナノメートルは10億分の1メートルという極めて微細な単位です。この技術は、現在の最先端である7nmや5nmプロセスをさらに超えるもので、スマートフォン向け高性能プロセッサやAI用アクセラレータなど、次世代の高度な半導体に不可欠とされています。
このnmプロセス技術は、トランジスタの性能向上と省電力化を飛躍的に進める革新的な技術です。 たとえば、IBMが2021年に発表した2nm試作チップのデータによると、7nm世代と比較して、同じ電力で45%の性能向上、または同じ性能で75%の消費電力削減が可能とされています。 この次世代のnmプロセス技術を実現するためには、ゲートオールアラウンド(GAA)トランジスタなどの新しい構造が不可欠であり、世界中の主要メーカーがその開発競争を繰り広げています。
なぜ半導体の微細化は重要?性能向上と省電力化の歴史
半導体の微細化は、コンピューティング性能の向上と電力消費の削減という、二つの主要な目標を達成するために不可欠です。この微細化の歴史は、トランジスタの小型化と集積密度の向上によって特徴づけられます。たとえば、2010年代初頭には22nmプロセス技術が主流となり、スマートフォンやPCの性能向上に大きく貢献しました。しかし、トランジスタをさらに小さくすると、電流が漏れてしまうリーク電流の問題が顕在化し、性能向上の障壁となりました。
この課題を克服するため、半導体業界はフィン型電界効果トランジスタ(FinFET)のような新しい構造を導入しました。これにより、ゲートがチャネルを複数の側面から囲むことで、電流制御能力が大幅に向上しました。さらに微細化が進み、現在では7nmプロセス技術が広く普及し、AIやデータセンターなどの高性能計算分野で不可欠な技術となっています。プロセス技術の進化は、半導体の性能を飛躍的に向上させると同時に、電力効率も高めるため、現代のデジタル社会において非常に重要な役割を担っています。
「2nm」は実際の長さではない?プロセスルールの数字が示す意味
半導体のプロセスルールにおける「2nm」や「3nm」といった数字は、物理的なゲート長や回路線幅の長さを直接示すものではありません。これは、特定の技術世代や性能の指標として用いられる「ノード」の名称であり、歴史的な経緯から微細化の度合いを示す便宜的な「ルール」として使われています。たとえば、かつてのプロセスルールでは、ゲート長やハーフピッチ(回路の間隔)がその数字に近似していましたが、FinFET構造の導入などにより、実際の物理的寸法とプロセスルール番号との乖離が進みました。現在では、同じノード番号でもメーカーによって実際のトランジスタ密度や性能が異なる場合があります。そのため、プロセスルール番号はあくまで技術世代を示す目安として理解することが重要です。このノードの概念は、半導体技術の進化とともに複雑化しており、単なる物理的なサイズではなく、トランジスタの集積度、性能、消費電力など、総合的な技術レベルを示すものとして認識されています。
2nmプロセスの鍵を握る新技術「GAAトランジスタ」の仕組み
2nmプロセス実現の鍵となるのが、次世代トランジスタ技術であるGAA(Gate-All-Around)トランジスタです。GAAトランジスタは、従来のFinFET構造では難しかった微細化における電流制御能力の向上を可能にします。現在のFinFET構造は、3nmプロセスや4nmプロセスなどの最先端技術で広く採用されていますが、さらなる微細化に伴うリーク電流の増大という課題を抱えています。GAAトランジスタは、チャネルをゲートが周囲から完全に覆う構造をしているため、FinFETよりも格段に優れた電流制御能力を発揮し、トランジスタの性能向上と消費電力の削減に貢献します。この新技術により、2nmプロセスにおいて高性能かつ低消費電力な半導体チップの製造が可能になると期待されています。
電流の制御能力を向上させるGAA構造とは
GAA(Gate-All-Around)構造は、次世代半導体の微細化において、電流制御能力を飛躍的に向上させる革新的なトランジスタ構造です。従来のFinFET(Fin Field-Effect Transistor)構造では、ゲートがチャネルの三方向を覆うことで電流の漏れ(リーク電流)を抑制していましたが、さらなる微細化、特に2nmプロセスのような極限的な領域では、リーク電流を完全に制御することが限界に達していました。これに対し、GAA構造は、チャネルをナノシートと呼ばれる薄い層状の構造で形成し、その周囲をゲート電極が360度完全に囲むことで、チャネルに対するゲートの制御力を最大化します。これにより、トランジスタがオフの状態のときに電流が漏れ出すのを効果的に防ぎ、オンの状態ではより多くの電流を効率的に流すことが可能になります。具体的には、FinFETと比較してゲートとチャネルの接触面積が大幅に増加するため、リーク電流を劇的に削減しつつ、駆動電流を向上させることができます。この優れた電流制御能力は、半導体の消費電力削減と高性能化に直結し、2nmプロセスの実現に不可欠な技術とされています。GAA構造の採用は、より高速で電力効率の高いAIチップやモバイルプロセッサなどの開発を可能にし、次世代の電子機器の性能向上に大きく貢献すると期待されています。
従来のFinFET構造との決定的な違い
FinFET構造とGAAトランジスタ構造の決定的な違いは、ゲートがチャネルを囲む方向と、それによる電流制御能力の向上にあります。FinFET(Fin Field-Effect Transistor)は、チャネル領域が垂直に立ち上がる「フィン」状の構造を持ち、ゲート電極がそのフィンを3方向から囲むことで電流を制御していました。この3方向からの制御により、従来の平面型トランジスタと比較して、リーク電流の抑制とスイッチング速度の向上が実現されました。
一方、GAA(Gate-All-Around)トランジスタは、ゲート電極がチャネルの全方向、つまり4方向から完全に囲む構造を採用しています。これにより、FinFETよりもさらに精密な電流制御が可能となり、特に微細化が進んだ際のリーク電流の増大という課題を克服できます。
FinFETでは、複数のフィンを横に並べることで電流量を調整していましたが、GAAでは、チャネルをナノシートと呼ばれる薄いシート状にして複数枚垂直に積層することで、より高い集積度と電流制御能力を実現しています。 このため、GAAはFinFETの限界を超え、2nmプロセスのような超微細な半導体製造において、高性能かつ低消費電力なチップを実現する鍵となる技術として期待されています。
2nmプロセスの製造が極めて困難とされる3つの理由
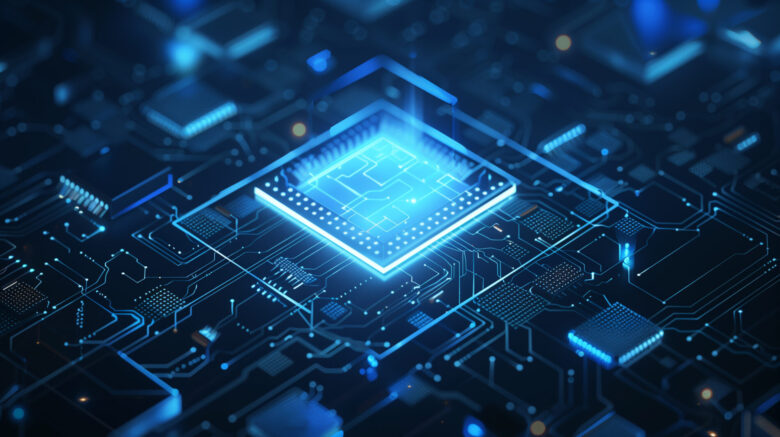
2nmプロセスの製造は、ナノメートルスケールの極めて微細な領域での複雑な加工を伴うため、非常に困難を伴います。まず、ナノシートの精密な加工に超高精度な技術が必要であり、わずかな誤差も許されません。また、リーク電流を防ぐために、新しい材料の導入や新しい構造設計が不可欠ですが、これには材料科学とプロセス技術の大きな進歩が必要です。最後に、これらの微細な構造を大量に生産するための最先端の露光技術や、それに伴う高い歩留まりを確保することが極めて難しいのです。このため、製造コストの増大や技術的ハードルの高さが課題として挙げられます。
ナノシートの精密な加工に求められる超高精度技術
2nmプロセスの実現には、ナノシートと呼ばれる薄い層状の構造を極めて高い精度で加工する技術が不可欠です。ナノシートはゲート電極がチャネルを四方から完全に囲むGAA(Gate-All-Around)構造においてチャネルとして機能するため、その形状や寸法がトランジスタの性能に直接影響を与えます。例えば、わずかな厚さの不均一さや幅の変動が、リーク電流の増加や性能のばらつきにつながる可能性があるのです。 したがって、ナノシートの成膜やゲート電極の形成には、原子レベルでの厳密な制御が求められます。
具体的には、ナノシートの積層枚数やそれぞれのシートの幅を精密に調整することで、トランジスタの性能を柔軟に設計できるという利点がある一方で、その製造には高度な技術が要求されます。 tsmcをはじめとする半導体メーカーは、このナノシート加工技術を確立するために多大な研究開発を進めており、例えばtsmcは2nmプロセス向けナノシートトランジスタの技術完成度が目標の80%以上を達成したと発表しています。 これは、高精度なエッチング技術や成膜技術、そしてこれらのプロセスを統合する複雑な製造フローが必要であることを示しています。このような超高精度技術がなければ、2nmプロセスで期待される高性能かつ低消費電力な半導体チップの量産は困難なのです。
リーク電流を防ぐための新材料導入と課題
リーク電流の抑制は、半導体の微細化を進める上で避けて通れない課題であり、2nmプロセスでは特に重要です。トランジスタのサイズが小さくなると、ゲートとチャネル間の距離も縮まり、電子が意図せずチャネルを通り抜けてしまう「トンネル効果」によるリーク電流が発生しやすくなります。この問題を解決するため、従来の材料では対応が難しくなっていることから、新しい高誘電率(High-k)材料の導入が不可欠です。例えば、High-kゲート絶縁膜として注目されている酸化ハフニウム(HfO2)などの材料は、高い誘電率を持つことでゲート絶縁膜を薄くしてもリーク電流を抑制し、トランジスタの性能を維持できます。しかし、これらの新材料は、既存の製造プロセスとの相性が悪く、加工が難しいという課題があります。特に、High-k材料とゲート電極との界面制御は非常に複雑で、界面準位(界面に存在する電子のエネルギー準位)の発生を防ぎ、安定した電気特性を確保するための技術開発が求められます。また、ibmも2nmチップの試作段階で、これらの材料技術の導入と最適化に取り組んでいると見られます。これらの新材料を効率的に導入し、量産化につなげるには、材料科学とプロセス技術における革新的な進歩が不可欠です。
量産化の鍵となる最先端の露光技術
2nmプロセスにおける量産化の鍵は、最先端の露光技術にあります。特にEUV(極端紫外線)露光技術は、微細な回路パターンをシリコンウェハーに転写するために不可欠な存在です。EUV露光は、波長13.5nmという極めて短い光を使用することで、これまでの光露光では不可能だった2nmという超微細な加工を可能にします。しかし、EUV露光装置は非常に高価であり、その導入コストは半導体メーカーにとって大きな負担となります。例えば、ASML社の最新EUV露光装置「High-NA EUV」は、1台あたり約3億8,000万ドル(約580億円)の価格がすると言われています。さらに、EUV露光には、極めて高い精度での位置合わせや欠陥管理、そしてマスク(原版)の高品質化が求められます。わずかな異物やマスクの欠陥が、大量の不良品を生み出し、量産化の大きな障害となるからです。Rapidus社のような企業は、このEUV露光技術をいち早く導入し、2nmプロセスの実用化と量産化を目指しています。露光プロセスの最適化と歩留まりの改善が、2nmプロセスの成功と、それによる高性能半導体の量産に直結するため、この分野での技術革新は今後も続くでしょう。
世界の主要メーカーによる2nmプロセス開発競争の最前線
世界中で半導体微細化競争が激化しており、特に2nmプロセス技術は次世代半導体の性能を左右する重要なカギとなっています。この開発競争を牽引しているのは、TSMC、Samsung、Intelといった世界の主要半導体メーカーです。TSMCは、2nmプロセスの量産を2025年に開始する計画を発表しており、台湾の複数の場所で製造拠点の建設を進めています。一方、Samsungも2025年の2nmプロセス量産化を目指しており、ゲート・オール・アラウンド(GAA)トランジスタ技術を先行して導入するなど、積極的な姿勢を見せています。また、Intelは2nm相当のプロセス技術「Intel 20A」の開発を完了しましたが、量産はキャンセルされ、次世代プロセッサ「Arrow Lake」での採用を取りやめて外部ファウンドリーに委託することを決定しました。これにより、Intelは18Aプロセスノードにリソースを集中する見込みです。Intelは独自のパッケージング技術も活用しながら競争に挑んでいます。日本でも、次世代半導体の国産化を目指すラピダスが、TSMCやIBMと連携し、2027年頃の2nmプロセス量産化を目指しています。ラピダスは、特にGAA構造の採用や、EUV露光技術の導入に力を入れており、日本における半導体産業の復興に貢献することが期待されています。これらのメーカーは、単にチップを微細化するだけでなく、GAAトランジスタのような新しい構造の導入や、EUV露光装置の最適化、そして新しい材料の採用など、多岐にわたる技術革新を推進しています。この開発競争は、高性能かつ低消費電力な半導体の供給を加速させ、AI、自動運転、5G/6Gといった最先端技術の進化に不可欠な役割を果たすでしょう。
2nmプロセスの実用化で私たちの生活はどう変わる?
2nmプロセスの実用化は、私たちの日常生活に想像以上の変化をもたらします。まず、スマートフォンやパソコンなどのデバイス性能が飛躍的に向上し、より高速でスムーズな操作が可能になるでしょう。例えば、どこでもAIを活用した高度な画像処理や動画編集が遅延なく行えるようになり、モバイルデバイスの可能性がさらに広がります。自動運転車の分野では、リアルタイムでの複雑なデータ解析がより高精度かつ迅速に行えるようになり、安全性と信頼性が向上します。また、医療分野では、AIを活用した診断支援システムや、ゲノム解析の高速化などにより、個別化医療の発展が加速するでしょう。データセンターの性能も向上するため、クラウドサービスの処理能力が強化され、私たちのデジタルライフはより快適になります。このように、2nmプロセスは、私たちの身の回りにあるあらゆる電子機器やサービスを根底から進化させ、よりスマートで効率的な社会の実現に貢献するのです。
まとめ
2nmプロセスは、半導体チップの回路線幅を2ナノメートル級まで微細化する次世代の製造プロセス技術です。これは技術世代の名称であり、実際の物理的寸法を示すものではありませんが、トランジスタの性能向上と省電力化を飛躍的に進める革新的な技術として期待されています。2nmプロセスの実現には、GAAトランジスタのような新しい構造の導入が不可欠であり、世界中の主要メーカーがその開発競争を繰り広げています。2nmプロセスは、AI、自動運転、5G/6Gといった最先端技術の進化を加速させ、私たちの生活をより豊かで便利なものに変える可能性を秘めているのです。
用語解説
ナノメートル(nm)
長さの単位。1nm=10億分の1メートル。半導体の微細化技術を表す指標として使われる。
プロセスルール(プロセスノード)
半導体製造世代を示す呼び方。数字(2nm, 5nmなど)は必ずしも実際の回路寸法を意味せず、技術世代の目安。
トランジスタ
半導体チップの基本素子。電流のオン・オフを制御する「スイッチ」の役割を持ち、論理回路や記憶に使われる。
リーク電流
トランジスタが「オフ」の状態でも電流が漏れてしまう現象。微細化が進むと深刻化する。
FinFET(フィン型電界効果トランジスタ)
微細化の限界を突破するため導入された構造。チャネルを「フィン(ひれ)」のように立ち上げ、ゲートが三方向から囲むことでリーク電流を抑える。
GAAトランジスタ(Gate-All-Around)
次世代トランジスタ構造。チャネルをゲートが四方360度から完全に囲み、FinFET以上に電流制御が可能。2nm世代のカギとなる技術。
ナノシート
GAAトランジスタでチャネルとして使われる極薄の層。複数を積層し、ゲートが周囲を囲むことで高性能・低消費電力を実現。
High-k材料(高誘電率材料)
ゲート絶縁膜に使われる新材料。酸化ハフニウム(HfO₂)などが代表例で、リーク電流を抑えながらトランジスタの微細化を可能にする。
EUV露光(Extreme Ultraviolet Lithography)
波長13.5nmの極端紫外線を使った最新の半導体露光技術。2nmプロセスのパターン形成に不可欠だが、装置は非常に高額(1台数百億円)。
フォン・ノイマン・ボトルネック
従来型コンピュータで「CPU(演算)とメモリ(記憶)が分離」しているために、データのやり取りが処理速度や電力効率の足かせになる問題。

西進商事コラム編集部
西進商事コラム編集部です。専門商社かつメーカーとしての長い歴史を持ち、精密装置やレーザー加工の最前線を発信。分析標準物質の活用も含め、さまざまなコラム発信をします。
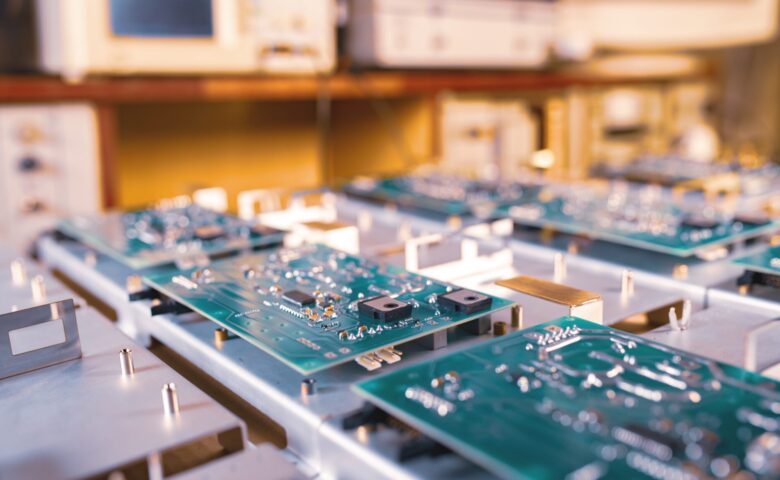
ファウンドリとは?半導体業界での役割やOSATとの違い、メリットを解説
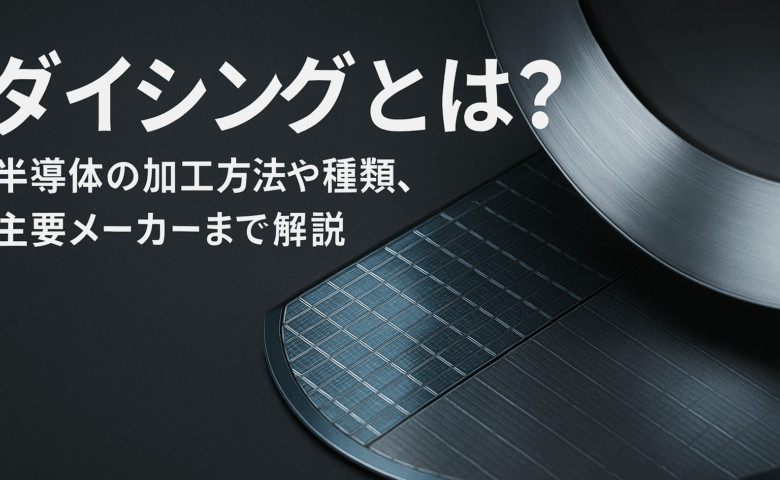
ダイシングとは?半導体の加工方法や種類、主要メーカーまで解説