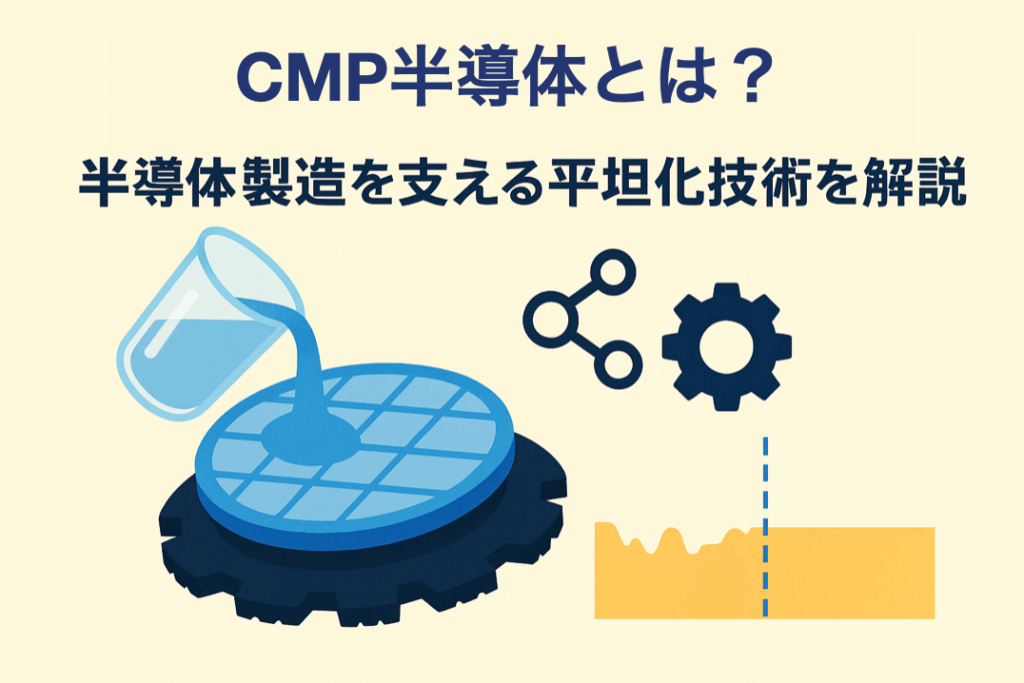
CMPとは、Chemical Mechanical Polishing(化学機械研磨)の略称で、半導体ウェーハの表面を化学的および機械的な作用によって平坦化する技術です。
半導体チップは、絶縁膜や金属配線など多数の薄膜を積み重ねて作られますが、各層を形成する過程で表面に凹凸が生じます。
この凹凸をCMPによって平坦にすることで、後続のフォトリソグラフィ工程での焦点ずれを防ぎ、微細で信頼性の高い回路を形成することが可能になります。
CMPとは、半導体の多層化と高性能化を実現するために不可欠な基盤技術の一つです。
半導体製造に不可欠なCMP技術の基本的な役割
半導体製造におけるCMP技術の基本的な役割は、ウェーハ表面をナノメートル単位で極めて平坦にすることです。
半導体回路は、シリコンウェーハという基板の上に、写真技術を応用したフォトリソグラフィ工程を何度も繰り返して形成されます。
しかし、薄膜を重ねるたびに表面には微細な凹凸が生じてしまい、この凹凸が残ったままだと次の回路パターンを焼き付ける際に焦点が合わなくなります。
CMPは、スラリーと呼ばれる研磨剤を用いて基板表面を精密に研磨し、この凹凸を解消する重要な役割を担っています。
CMPによる平坦化の仕組みを2つの作用で解説
CMPによる平坦化は、化学的な作用と機械的な作用という2つの相乗効果によって実現されます。
CMPプロセスは、研磨パッドを取り付けた定盤とウェーハを保持するヘッドを持つCMP装置内で行われます。
まず、スラリーに含まれる化学成分がウェーハ表面の膜と化学反応を起こし、表面を柔らかくしたり、溶解しやすい状態に変質させます。
次に、研磨パッドとウェーハを相対的に回転させながら圧力を加え、スラリー中の砥粒によって物理的に研磨し、表面の凸部を選択的に除去します。
この仕組みの詳細は、装置メーカーが公開している動画でも確認できます。
研磨の鍵を握る液体「CMPスラリー」の成分と機能
CMPスラリーとは、研磨プロセスにおいて中心的な役割を果たす特殊な液体です。
スラリーは主に、ナノメートルサイズの微細な砥粒と、様々な化学薬品が含まれた薬液から構成されています。
砥粒は、シリカ(SiO2)やセリア(CeO2)、アルミナ(Al2O3)などが用いられ、ウェーハ表面を物理的に削り取る機械的な研磨作用を担います。
一方、化学薬品は、研磨対象となる膜の材質に応じて、表面を化学的に溶解させたり、酸化させて研磨しやすい状態に変質させたりする化学的作用を担います。
この砥粒と化学薬品の組み合わせを最適化することで、目的の膜を選択的かつ高精度に平坦化することが可能です。
半導体の多層化を実現するCMP技術が利用される主な工程
CMP技術は、半導体の複雑な多層構造を形成する上で、様々な製造工程で活用されています。
代表的な例の一つが、トランジスタ同士を電気的に分離するためのSTI(ShallowTrenchIsolation)形成工程です。
この工程では、ウェーハに溝を掘り、絶縁膜で埋めた後に不要な部分をCMPで除去し、平坦な素子分離構造を形成します。
また、多層配線構造において各配線層の間を絶縁する層間絶縁膜(ILD)の平坦化や、銅(Cu)配線を形成するダマシン法においても、埋め込まれた余分な銅を除去するためにCMPが不可欠な工程となっています。
高精度な平坦化を実現する上でのCMP技術の課題
半導体の微細化と高性能化が進むにつれて、CMP技術にはより高いレベルの平坦性が求められており、いくつかの技術的課題が存在します。
その一つが、ウェーハ全面にわたって均一な研磨レートを維持することの難しさです。
また、研磨されすぎによるディッシングやエロージョンといった形状不良の発生も課題となります。
さらに、CMPプロセス中に発生する微細なスクラッチ(傷)や、スラリーの砥粒、研磨屑などのパーティクルによる汚染は、チップの歩留まりを著しく低下させる深刻な欠陥につながるため、これらの発生をいかに抑制するかが重要です。
研磨レートのばらつきを精密に制御する難しさ
CMPプロセスにおける大きな課題は、ウェーハ全面で研磨レートを均一に保つことの難しさにあります。
ウェーハの中心部と周辺部では、研磨パッドとの相対速度や圧力のかかり方が異なるため、研磨レートにばらつきが生じやすくなります。
このばらつきは、研磨後の膜厚の不均一につながり、デバイスの性能や信頼性に直接影響を与えます。
この問題を解決するため、CMP装置では研磨ヘッドの圧力分布を細かく調整したり、スラリーの供給方法を最適化したりするなどの工夫が凝らされています。
半導体の高精度な製造を実現するには、これらのパラメータを精密に制御し、常に安定した研磨結果を得る技術が求められます。
微細な傷(スクラッチ)や汚染を防ぐ品質管理
CMP工程における品質管理で極めて重要なのが、スクラッチや汚染の防止です。
研磨時にスラリー中の粗大な砥粒や凝集した粒子、外部からの異物が介在すると、ウェーハ表面に微細な傷であるスクラッチが発生します。
このスクラッチは、回路の断線やショートを引き起こす原因となり、半導体チップの不良に直結します。
また、研磨後にウェーハ表面に残存するスラリー成分や研磨屑などのパーティクルも汚染源となります。
そのため、CMP後には極めて清浄度の高い薬液と純水を用いた多段階の洗浄工程が必須であり、スクラッチの発生を抑えるスラリーの開発と共に、厳格なパーティクル管理が行われています。
まとめ
CMPは、化学作用と機械作用を融合させ、半導体ウェーハ表面をナノメートルレベルで平坦化する、現代の半導体製造に不可欠な技術です。
トランジスタの素子分離から多層配線の形成に至るまで、様々な工程でその役割は重要性を増しています。
半導体の微細化・三次元化がさらに進む中、ディッシングやエロージョンといった形状不良の抑制、スクラッチの低減など、CMPプロセスに対する要求はより高度化しています。
このような要求に応えるため、CMP装置や研磨パッドの改良とともに、3Mをはじめとする化学メーカーによる高性能なスラリーの開発など、関連技術全体の継続的な革新が半導体産業の発展を支えています。
用語まとめ
CMP(Chemical Mechanical Polishing)
化学機械研磨の略。化学的な反応と機械的な研磨を組み合わせて、半導体ウェーハ表面を平坦化する技術。微細加工で欠かせない工程。
平坦化(Planarization)
表面の凹凸をなくして平らにすること。次のフォトリソグラフィ工程で焦点を正確に合わせるために必要。
シリコンウェーハ(Silicon Wafer)
半導体デバイスの基板となる薄い円盤状のシリコン。チップの土台となる重要素材。
フォトリソグラフィ(Photolithography)
光を使って回路パターンをウェーハ上に転写する工程。CMPで表面が平坦でないと正確にパターンを焼き付けられない。
スラリー(Slurry)
CMPで使われる研磨液。ナノサイズの砥粒(シリカ・セリア・アルミナなど)と化学薬品を混合した液体で、研磨と化学反応を同時に進行させる。
研磨パッド(Polishing Pad)
CMP装置に取り付けられる研磨用のパッド。ウェーハと接触し、スラリーを介して物理的に表面を削る役割を持つ。
ウェーハキャリア(Carrier / Head)
CMP装置でウェーハを固定し、圧力を均等にかける部分。研磨均一性を保つための重要機構。
化学作用(Chemical Action)
スラリー内の薬品がウェーハ表面の膜と化学反応を起こし、溶解・酸化して柔らかくするプロセス。
機械作用(Mechanical Action)
スラリー中の砥粒と研磨パッドの摩擦によって表面を物理的に削るプロセス。化学作用とセットで平坦化を実現。
STI(Shallow Trench Isolation)
トランジスタを電気的に分離するための構造。ウェーハに浅い溝を掘り、絶縁膜で埋めた後にCMPで表面を平坦化する。
ILD(Inter-Layer Dielectric)
多層配線間の絶縁膜。CMPで平坦化して、次の配線層の形成を正確に行えるようにする。
ダマシン法(Damascene Process)
銅(Cu)配線を形成する製造方法。溝に金属を埋め込み、余分な部分をCMPで削って仕上げるプロセス。
ディッシング(Dishing)
CMP中に金属部分が削れすぎて中央が凹んでしまう欠陥。配線の厚み不均一の原因になる。
エロージョン(Erosion)
絶縁膜の部分が過剰に削られる現象。CMP後の膜厚ばらつきの要因。
研磨レート(Removal Rate)
単位時間あたりに削られる膜厚。材料やスラリー成分、圧力などで変化し、制御が難しいパラメータ。
スクラッチ(Scratch)
研磨時に発生する微細な傷。スラリー中の粗大粒子や異物が原因で発生し、歩留まり低下の原因になる。
パーティクル(Particle)
CMP後に残る微細な粒子汚染。チップ表面に残ると電気的欠陥を引き起こすため、厳密な洗浄が必要。
洗浄工程(Cleaning Process)
CMP後に行う薬液・純水洗浄プロセス。スラリーやパーティクルを完全に除去して次工程への影響を防ぐ。
ディフェクト(Defect)
CMP工程中や後に発生する欠陥の総称。ディッシング、スクラッチ、エロージョンなどが代表的。
3M
CMP用スラリーや研磨パッドの大手メーカー。半導体業界で高精度CMP材料の開発をリードしている。

西進商事コラム編集部
西進商事コラム編集部です。専門商社かつメーカーとしての長い歴史を持ち、精密装置やレーザー加工の最前線を発信。分析標準物質の活用も含め、さまざまなコラム発信をします。
