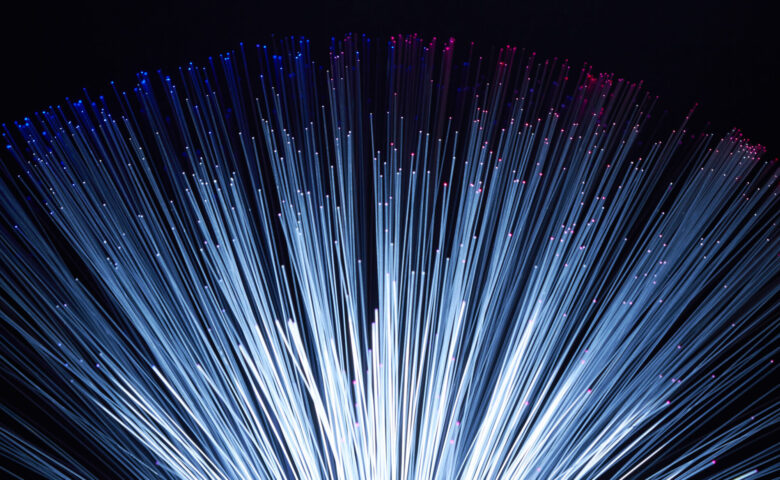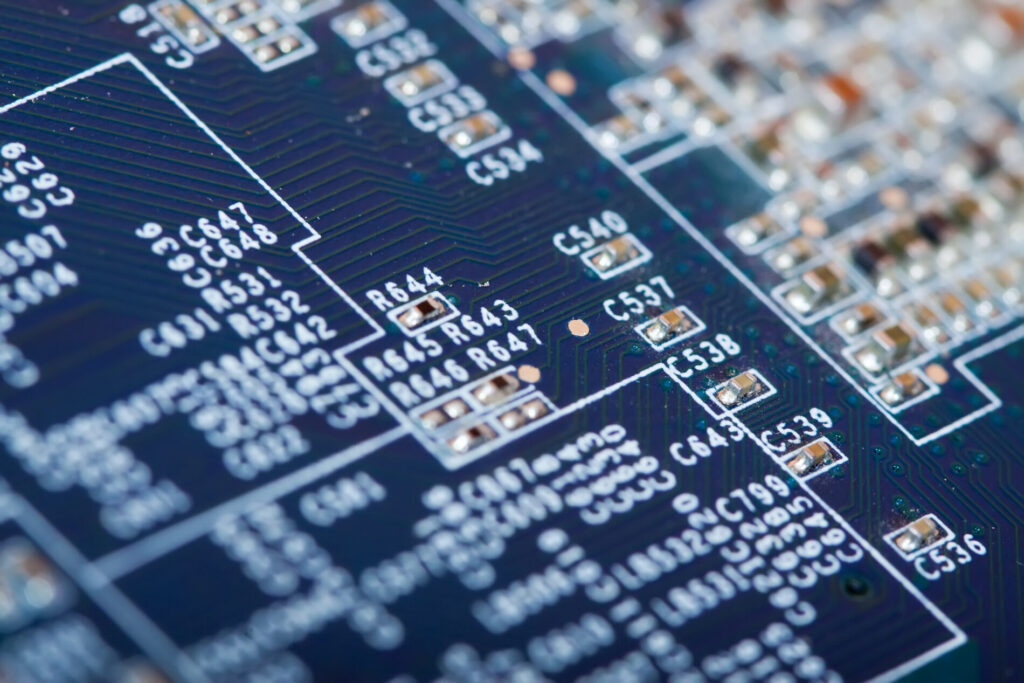
- INDEX目次
目次【非表示】
アングストローム技術とは、半導体のさらなる微細化を追求する技術分野を指します。現在、5ナノメートル世代の半導体製造技術が市場に投入され、3ナノメートル世代の研究開発が進められており、アングストローム世代はこれら一桁ナノメートル世代以降の技術を意味します。アングストロームという単位は0.1ナノメートル、つまり100億分の1メートルを表し、原子レベルでの精密な制御が求められる領域です。
半導体素子の微細化は、集積度の向上、スイッチング速度の高速化、そして消費電力の低減を可能にするため、半導体の性能向上に不可欠です。しかし、従来の平面型トランジスタでは微細化の限界が近づいており、インテルやIMECといった主要な半導体メーカーは、GAA(Gate-All-Around)構造やCFET(相補型FET)といった新たなトランジスタ構造の開発を通じて、アングストローム世代の実現を目指しています。この技術により、原子極限に迫る微細化が可能となり、次世代の高性能で低消費電力な半導体の実現が期待されています。
そもそもアングストローム(Å)とは?ナノメートルとの違いを解説
アングストローム(Å)は、原子や分子の大きさを表す際に用いられる長さの単位で、1アングストロームは1メートルの100億分の1、つまり0.1ナノメートルに相当します。ナノメートル(nm)は1メートルの10億分の1であり、1ナノメートルは10アングストロームとなります。このように、アングストロームはナノメートルよりもさらに小さな長さを表す単位です。
アングストロームは、電磁波の波長、膜の厚さ、表面の粗さ、結晶格子などの非常に微細な長さを計量する際に使用されます。かつては分光学などの分野で広く使われていましたが、国際単位系(SI)では推奨されておらず、主に半導体産業などの特定の分野でその利便性から現在も使用されています。
日本では、計量法により「電磁波の波長、膜厚又は物体の表面の粗さ若しくは結晶格子に係る長さの計量」にのみ使用が認められている法定計量単位です。国際単位系においては、アングストロームの使用は段階的に廃止され、2019年以降の現行版では一切記載がありません。しかし、その利便性から理化学や工業分野で使われることがあります。
半導体の性能向上に不可欠なアングストローム技術の重要性
半導体の性能を向上させるためには、アングストローム技術が不可欠です。この技術は、半導体のさらなる微細化を可能にし、より高密度な集積回路を実現します。微細化が進むことで、半導体チップに搭載できるトランジスタの数が増加し、処理能力の向上と消費電力の削減が両立されます。特に、原子レベルでの精密な制御が求められるアングストローム世代の半導体製造では、従来の技術では達成できなかった性能を引き出すことが可能になります。これにより、スマートフォンやAIデバイス、データセンターなど、幅広い分野で次世代の高性能な電子機器が実現されると期待されています。
限界を迎える「ムーアの法則」を継続させる新技術
ムーアの法則は、集積回路上のトランジスタ数が約2年ごとに倍増するという経験則で、半導体業界の発展を長らく牽引してきました。しかし、近年この法則は物理的な限界に直面しています。トランジスタの微細化が原子レベルに近づくにつれて、量子力学的な効果や熱問題が顕在化し、従来の微細化技術だけでは性能向上が困難になってきているためです。具体的には、現在の最先端プロセスではゲート長が数ナノメートルに達し、電子がトンネル効果で漏れ出すなどの問題が発生しています。このような課題を克服し、ムーアの法則の継続、つまり半導体性能の継続的な向上を可能にするのが、アングストローム技術です。
アングストローム技術では、従来のFinFET(フィン型電界効果トランジスタ)構造に代わり、GAA(Gate-All-Around)構造やCFET(相補型FET)などの新しいトランジスタ構造が採用されます。GAA構造は、ゲートがチャネルを四方から完全に囲むことで、より優れた静電制御を実現し、リーク電流を抑制します。さらに、CFETはN型とP型のトランジスタを積層することで、より高密度な集積とさらなる性能向上を可能にします。これらの新技術は、原子レベルでの精密な制御を可能にし、ムーアの法則が予測するペースでの半導体性能の向上を、今後も継続させるための鍵となります。
消費電力の削減と処理性能の向上を両立
アングストローム技術による半導体の微細化は、消費電力の削減と処理性能の向上を両立させる上で極めて重要です。半導体における微細化は、回路内のトランジスタ密度を高めることで、より多くのトランジスタを一つのチップに集積することを可能にします。これにより、データの処理速度が向上し、結果として処理性能が飛躍的に高まります。
また、微細化はトランジスタの動作に必要な電力を低減させる効果もあります。トランジスタが小さくなるほど、スイッチングに必要な電力量が減少し、チップ全体の消費電力を抑制できます。例えば、次世代のトランジスタ構造であるGAA(Gate-All-Around)構造では、従来のFinFETと比較して約50%の消費電力削減と35%の性能改善が見込まれています。 さらに、GAAの後継として期待されるCFET(相補型FET)では、PMOSとNMOSを垂直に積層することで、さらなるセルサイズの縮小と、低電力動作による省エネルギー効果が期待されています。
このように、アングストローム技術は、単に半導体を小さくするだけでなく、高性能化と省エネルギー化という、現代のデジタル社会に不可欠な二つの要素を同時に実現するための基盤となるのです。スマートフォンやAI、自動運転、IoTデバイスなど、高性能と低消費電力が求められるあらゆる分野で、アングストローム技術がその進化を支えることになります。
アングストローム時代を支える次世代トランジスタの構造
アングストローム時代を支える次世代トランジスタの構造には、従来のFinFET構造に代わるGAA(Gate-All-Around)構造が注目されています。FinFET構造では、ゲートがチャネルの3側面を囲んでいましたが、微細化が進むにつれて電流制御の限界が露呈しました。GAA構造では、ゲートがチャネルの4側面すべてを囲むことで、より強力な電流制御が可能になります。この構造は、リーク電流の抑制やスイッチング速度の向上に寄与し、半導体の性能向上に不可欠です。また、さらなる微細化を目指すCFET(相補型FET)の可能性も探られています。CFETは、N型FETとP型FETを積層することで、面積効率を大幅に向上させることを目指しています。これらの次世代トランジスタ構造は、アングストローム世代の半導体開発において重要な役割を担っています。
従来のFinFET構造からGAA(Gate-All-Around)構造へ
FinFET構造は、トランジスタのゲートがチャネルの3つの側面を取り囲むような立体構造を持ち、これによりゲートがチャネルをより効果的に制御し、リーク電流を抑制する役割を果たしてきました。しかし、半導体のさらなる微細化が進むにつれて、FinFET構造ではゲートとチャネルの接触面積を十分に確保することが難しくなり、電流制御能力の限界が露呈しました。特に、3ナノメートル以下のプロセスノードでは、この課題が顕著になります。
そこで注目されているのが、GAA(Gate-All-Around)構造です。GAA構造では、ゲートがチャネルの四方を完全に囲むことで、ゲートによる電流制御能力を大幅に向上させることが可能です。これにより、FinFET構造では難しかったリーク電流のさらなる抑制と、駆動電流の最大化が実現されます。GAA構造には、チャネルの形状に応じてナノシートやナノワイヤーといったバリエーションが存在し、特にナノシート構造はゲートの周囲に複数の薄いシート状のチャネルを積層することで、高い電流駆動能力と優れた静電特性を両立させることができます。
GAA構造への移行は、半導体メーカーにとって大きな技術的転換点となります。製造プロセスの複雑化や新たな材料の開発が必要となる一方で、アングストローム世代の半導体を実現し、次世代の高性能デバイスを支える上で不可欠な技術と位置付けられています。インテルは20A(2ナノメートル相当)プロセスでGAAFETを導入すると発表しており、TSMCやSamsungなどの主要メーカーも同様にGAA構造の導入を計画している状況です。
さらなる微細化を目指すCFET(相補型FET)の可能性
CFET(Complementary Field-Effect Transistor:相補型FET)は、次世代の半導体微細化を牽引する革新的なトランジスタ構造として注目されています。この技術は、GAA(Gate-All-Around)構造のさらに進化した形であり、n型FETとp型FETを垂直に積層する点が最大の特徴です。従来のGAAでは、n型とp型のトランジスタが横並びに配置されていましたが、CFETではこれらを縦方向に重ねることで、チップ上のデバイス密度を飛躍的に向上させることができます。これにより、トランジスタのセルサイズを大幅に縮小し、同じ面積により多くのトランジスタを集積することが可能になります。
CFETの導入は、微細化の物理的な限界に近づきつつある現状において、ムーアの法則をさらに延長するための有望な解決策と位置付けられています。 垂直積層構造により、デバイスの占有面積を削減しながら、性能向上と消費電力の削減を両立できる点が大きな利点です。 特に、スタンダードセルやSRAMセルの面積を大幅に縮小できると期待されており、imecなどの研究機関では、3nmプロセス以降の微細化に適した技術としてCFETの開発を進めています。
CFETの製造には、モノリシック方式とシーケンシャル方式の2つの主要な集積方式が検討されていますが、いずれの方式も新たな配線スキームや熱処理の最適化、高アスペクト比のエッチングなどの課題が存在します。 しかし、これらの課題を克服することで、CFETは2030年代には1nm以下のプロセスノードでの実用化が見込まれており、AI時代の発展を支える基盤技術となることが期待されています。
主要半導体メーカー各社による開発ロードマップと現状
主要半導体メーカー各社は、アングストローム技術の実現に向けて積極的な開発ロードマップを掲げています。例えば、Intelは、2024年に導入を計画していた20Aプロセス(2nm相当)を中止し、18Aプロセス(1.8nm相当)の開発に注力することを2024年9月に発表しました。18Aプロセスは2025年に量産開始予定とされており、初期生産には成功していると報じられています。
また、SamsungはGAA構造をいち早く導入し、すでに3nmプロセスの量産を2022年より開始しており、将来的にはサブ1nmプロセスの開発も視野に入れています。TSMCも3nmプロセスの量産を進め、2nmプロセスの開発に着手しており、2025年後半の導入を目指しています。これらの動きは、各社がアングストローム世代の半導体製造をいかに重視しているかを示しており、今後の技術競争がさらに激化することが予想されます。
アングストローム技術が実現する未来のテクノロジー
アングストローム技術は、半導体のさらなる微細化を可能にすることで、私たちの社会に革新的な変化をもたらします。例えば、AIの進化が加速し、より複雑なデータ処理や高度な学習能力を持つシステムが実現されるでしょう。これにより、自動運転技術の安全性向上や、医療分野におけるAI診断の精度向上が期待されます。
また、IoTデバイスの普及もさらに進み、あらゆるモノがインターネットに繋がり、よりシームレスでインテリジェントな社会が構築されます。個人の健康管理から都市インフラの最適化まで、生活のあらゆる側面でアングストローム技術が貢献する未来が描かれています。さらに、量子コンピューティングの発展にも寄与し、現在のスーパーコンピューターでは解決不可能な問題の解決や、新素材の開発など、科学技術の新たなフロンティアを開拓する可能性を秘めています。
まとめ
半導体技術は、アングストローム単位での微細化により、処理性能の向上と消費電力の削減を実現し、ムーアの法則の継続に貢献しています。この進化を支えるのは、GAA構造やCFETといった次世代トランジスタ技術の開発です。主要な半導体メーカーは、これらの技術を基盤とした開発ロードマップを推進しており、AIや高速通信、データセンターなど、幅広い分野で革新的なテクノロジーを創造する未来が期待されます。
用語解説
アングストローム(Å):1 Åは0.1ナノメートル(1メートルの100億分の1)。原子や分子の大きさを表すときに使われる長さの単位。
ムーアの法則:集積回路上のトランジスタ数は約2年ごとに倍増するという経験則で、半導体性能の進化を示す目安。
FinFET(フィン型電界効果トランジスタ):ゲートがチャネルの3方向を囲む構造。リーク電流を抑えられるが、微細化限界に近づいている。
GAA(Gate-All-Around)トランジスタ:ゲートがチャネルを4方向から完全に囲む構造。FinFETより強力な電流制御で高性能・低消費電力を実現。
CFET(Complementary FET):n型とp型のトランジスタを上下に積層する構造。面積効率を大幅に高め、1nm以下時代の有力技術。
リーク電流:トランジスタがオフの状態でも流れてしまう電流。微細化が進むと増加し、省電力化の障害となる。
トンネル効果:電子が障壁を量子的にすり抜ける現象。微細化でゲート長が短くなるとリーク電流の原因になる。
ナノシート:薄いシート状のチャネルを積層した構造。GAAの一形態で高い電流駆動能力を持つ。
ナノワイヤ:細い線状のチャネルを使う構造。GAAの一形態で微細化に適している。
imec(インター大学マイクロエレクトロニクスセンター):ベルギーの半導体研究機関。GAAやCFETなど次世代技術の研究開発を主導。

西進商事コラム編集部
西進商事コラム編集部です。専門商社かつメーカーとしての長い歴史を持ち、精密装置やレーザー加工の最前線を発信。分析標準物質の活用も含め、さまざまなコラム発信をします。
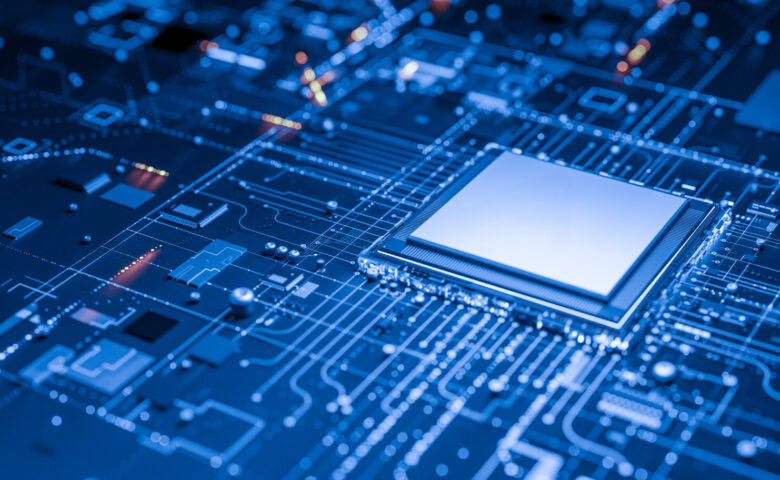
2nmプロセスとは?次世代半導体の仕組みや製造が難しい理由を解説
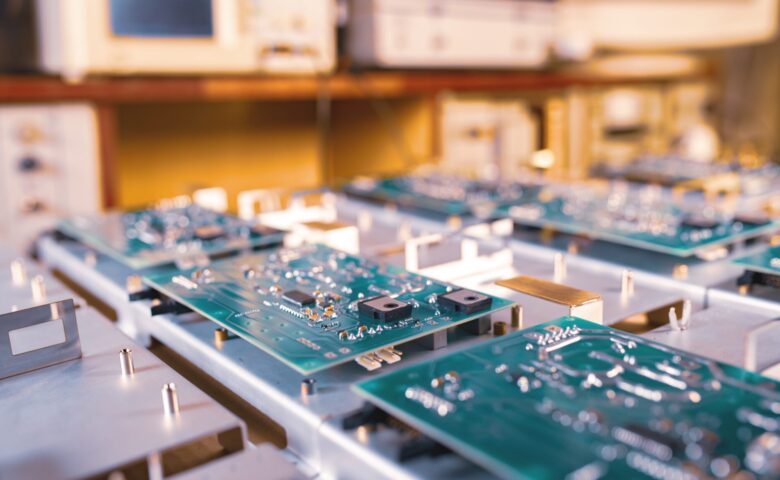
ファウンドリとは?半導体業界での役割やOSATとの違い、メリットを解説